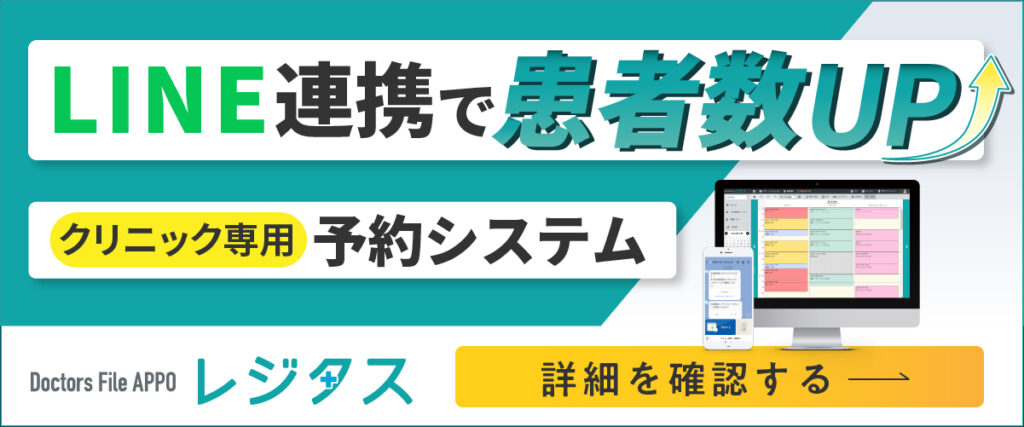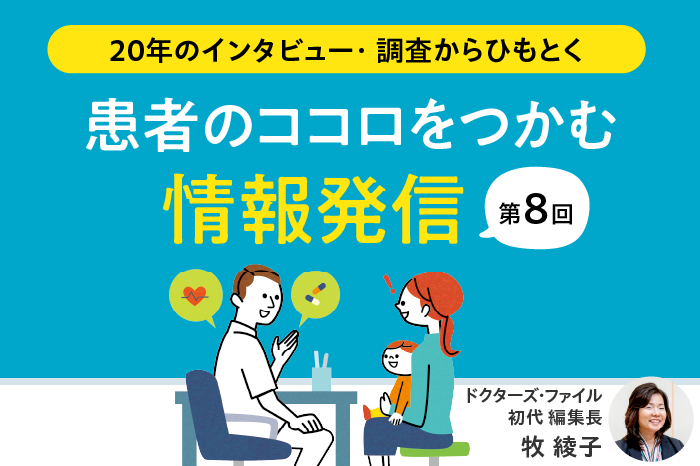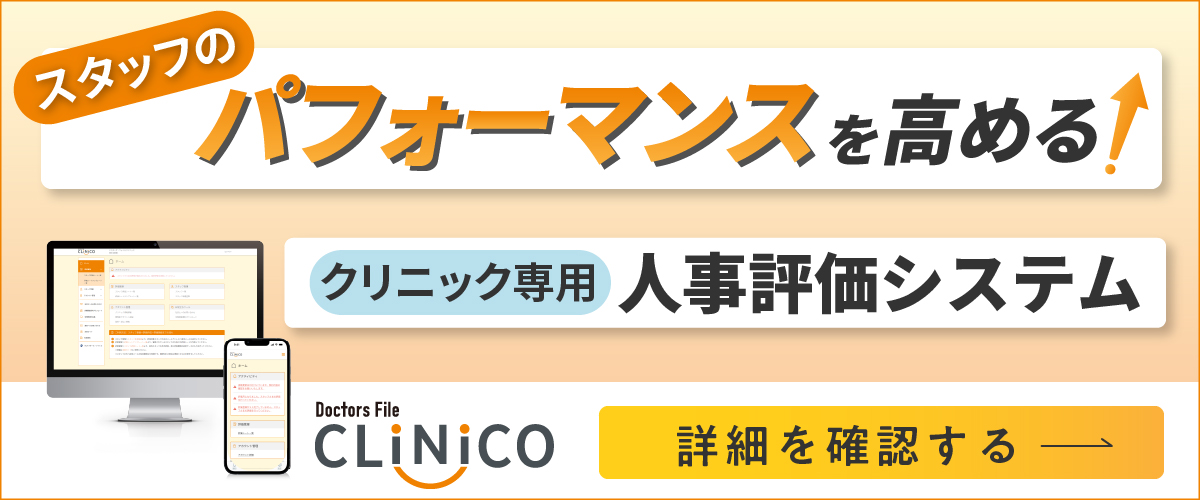「知りたい」と「伝えたい」とをつなぐ情報の懸け橋として
患者の「知りたい」とドクターの「伝えたい」をつなぐ「ドクターズ・ファイル」は、自分に合ったドクターに巡り会いたいという患者の願いと、患者を思うドクターの気持ちに寄り添ってきました。
このサービスを始めた当初は前例のない事業モデルだったこともあり、1カ月に1軒のクリニックからも取材の承諾をいただけない、ということもありました。それでも突き進んで来られたのは、信頼できる医療情報を必要としている患者の切なる要望が、私たち編集部に寄せられ続けていたからです。
このサービスは患者にとって絶対に必要なんだ! という強い信念のもと、自分たちに問い続けてきました。
――誰のために、何のために、どのように医療情報を伝えるべきなのか、と。
今この瞬間も、私たちの周りにはさまざまな病気や症状を抱えた人々がいて、知りたい医療情報や期待する医療サービスは内容もその深さも一人ひとり異なると感じます。私たちはそうしたきめ細かなニーズに丁寧に応えられるメディアをつくり上げていくことを使命とし、地域医療への安心感と信頼性を伝える役割を担い続けていけたらと願っています。
例えば、健康面で心配なことがあっても医療機関に足を運べずにいた人が、ドクターの考えやクリニックの雰囲気、設備、そこで働くスタッフのことを深く知ることで背中を押されて受診し、大事に至らずに済むこともあるかもしれない。難しい病気を患っている人が、どの病院のどのドクターを頼ればいいのかをもっと便利に調べられたら、より安心して手術に臨めるかもしれない。そんなふうに想いをはせながら、私たちはドクターの皆さまと一緒になって、正しい情報を提供したいと心を熱くするのです。
また、クリニックや病院、在宅で地域の医療を支えるため、多くのドクター・看護師・医療スタッフが強い信念を持って貢献されている姿も、私たちは日々の取材を通して目にしてきました。患者の期待に最良の形で応える、その一心で医療を提供されている姿や想いにふれるたび、私たちメディアがそのことをしっかりと伝えていかなければと身の引き締まる思いがします。
「ドクターズ・ファイル」のスタートから約20年、これまでに取材をさせていただいたドクターの数は約3万人に上ります。その間、特別編集書籍『頼れるドクター』、病院紹介サイト「ホスピタルズ・ファイル」といった各種メディアも展開してきました。今日では、ドクターの皆さまが患者に正しい医療情報を提供することが「当たり前」となりつつあり、「ドクターズ・ファイル」のつくりたかった世界観が実現されているという確かな手応えを感じています。
クリニック経営を包括的にサポートするプラットフォームを
医療情報メディアを軸に、ドクターの皆さまのご要望や期待に寄り添い、それに応える形で事業を拡大してきた私たちですが、ここ数年は先生方の抱える課題が、複雑かつ多様化しているのを感じています。その背景の一つに、「キュア(治療)からケア(予防)中心へ」と日本の医療が大きな転換期を迎えていることが挙げられると思います。コロナ禍を経て、誰もが健康の大切さを改めて感じたことも、その後押しになっているのは間違いありません。
「健康でいるために、病気になる前にドクターに相談したい」「自分の体は自分で守りたい」。
そんな人々の願いをかなえるには、ケアを担うクリニックの存在が不可欠であり、その役割はこれからますます大きくなっていくはずです。
だからこそ、私たちは孤軍奮闘するドクターの皆さまを支え、一緒にクリニック経営の課題解決に挑んでいきたいと願うのです。もちろん簡単でないことは重々承知ですが、「ありえない」を「当たり前」に変えてきた私たちなら、必ず先生方のお力になれると信じています。

ただ、そのためにはこれまでと同じやり方では通用しません。ケアの時代を乗り切るには、正しい医療情報の発信に加え、院内システムの構築や人材育成・採用のサポートなど、クリニックが抱える課題を包括的にサポートしていく必要があると考えました。そこで、今私たちが取り組んでいるのが、「マッチング」「院内業務DX」「HR」「コンサル」という4領域におけるプラットフォームサービスです。

まず「マッチング領域」では、患者のココロとドクターのココロをつなぐ懸け橋として、「ドクターズ・ファイル」や『頼れるドクター』、「ホスピタルズ・ファイル」をはじめとするメディア運営を行います。ドクターの専門性はもちろん、医療に対する価値観や地域への想いなど、「目に見えない部分」までも患者に伝えることで、双方にとって最適なマッチングの機会を創出します。
続く「院内業務DX領域」では、医療現場の業務プロセスや医療サービスの変革をめざしたサービスを展開しています。具体的には、クリニック専用情報共有アプリ「メディパシー」や、予約・患者管理システム「レジタス」、WEB予約受付機能「ドクターズ・ファイル アポ」、ホームページ制作サービス「ドクターズ・ファイル リンク」を提供するほか、オールインワンのキャッシュレス端末の導入サポートなども行っています。厚生労働省が医療DXを進める中で、先生方にとってデジタル化は喫緊の課題だと思いますので、そのサポートをさせていただきます。
また「HR領域」では、医療現場を支える「人」にまつわる課題解決をめざします。具体的には、クリニック専用人事評価・人材マネジメントシステム「ドクターズ・ファイル クリニコ」や、医療系求人情報サイト「ドクターズ・ファイル ジョブズ」、医療職向け転職支援サービス「ドクターズ・ファイル エージェント」などがあります。スタッフの採用・育成に悩むドクターは多いですが、その根本的な原因にフォーカスしたサービスを通じ、医療を提供する人たちが生き生きと働ける環境づくりを支えていければと思っています。
最後に「コンサル領域」では、未来のクリニック経営につながる情報を独自に研究し、この経営支援メディア「クリニック未来ラボ」として発信しています。患者情報や患者ニーズへの深い洞察力を持つ私たちならではの視点で、開業医や開業をめざすドクターのお役に立てたらと考えています。
「不」の本質を見つめ、新しい価値観や行動を生み出すこと
私たちが提供するサービスの根底にあるのは、医療に関係する人々の間にはびこる、不安・不信・不便……といった「不」を解決すること、そしてそれを「希望」に変えていきたいという想いです。そのためには、「不」の本質を見つめ、新たな価値観や行動を生み出す必要があり、そんな新しい医療文化を創造することが、自分たちに課せられたミッションだと考えています。
「ドクターズ・ファイル」が、ドクターと患者それぞれが抱える「不」を解決する糸口となったように、ドクターと患者間だけでなく、ドクターとスタッフ、スタッフ同士、医療職と介護職、クリニックと病院といった医療を通じて出会うすべての人たちの間にある「不」を「希望」に変えていきたい。それがギミックの存在意義であり、私たちにしかできないことだと信じています。
健康を願う人と守る人の「不」を「希望」に――その実現に向けて、私たちはこれからもドクターと患者の心に寄り添いながら、前進し続けます。
イラスト/古藤みちよ
<執筆者プロフィール>
牧 綾子(まき・あやこ)
ドクターズ・ファイル初代編集長、頼れるドクター編集長。株式会社リクルートの求人事業部にて10年間、事業・商品・営業の企画業務を担当。その後、株式会社ギミックにて「ドクターズ・ファイル」の立ち上げと『頼れるドクター』の創刊から携わる。開業医だった祖父と80歳を過ぎた今も総合病院で内科医として勤務する父の背中を見ながら、ドクターの医療に懸ける想いを肌で感じて育つ。また、2児の母として子育てを通じ医療情報の必要性を強く信じている。クライアントやユーザーに寄り添いながらメディアづくりをすることを大切にしている。