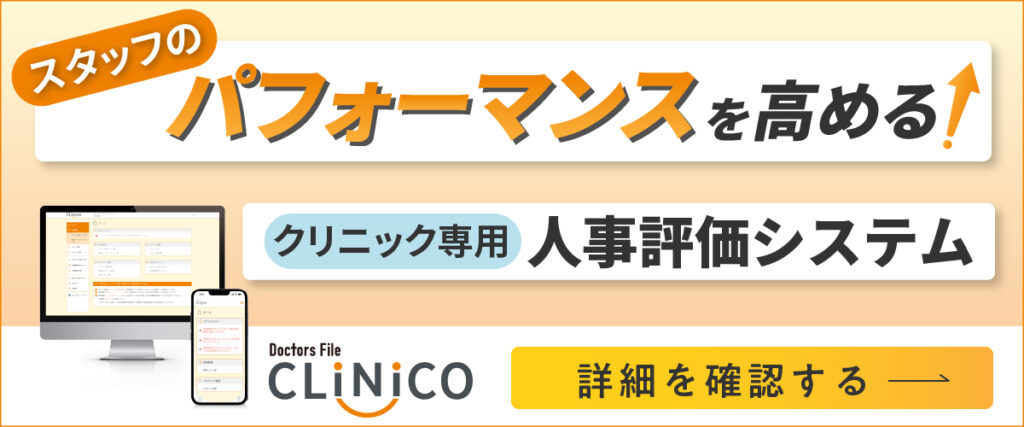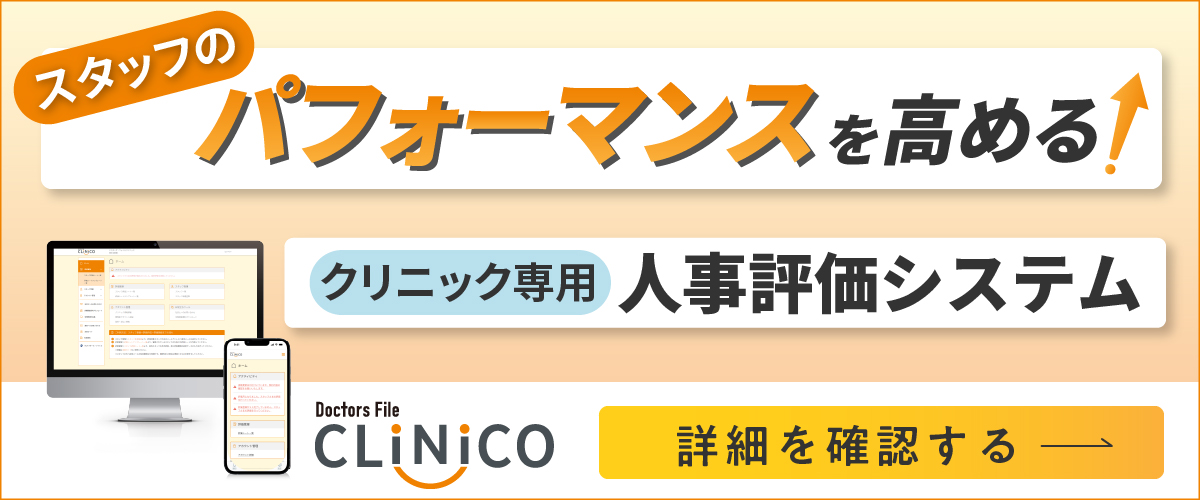クリニックのボーナス相場は?職種、地域、経営形態別に最新データで解説
クリニックのボーナス相場は、スタッフの職種や地域などで異なります。自院の状況を把握するためにも、まずは全国的な相場や傾向を知っておくことが大切です。
ここでは最新データをもとに、職種別、地域別、経営形態別に分けて解説します。
職種別
看護師や技師、事務職など、クリニックにはさまざまな職種が存在し、賞与にも差があります。 2023年(令和5年)に中央社会保険医療協議会が実施した「第24回医療経済実態調査(医療機関等調査)の報告 (令和5年11 月)」(※1)によると、一般診療所(個人と医療法人を合わせた全体)に所属する医師・職員に支給されたボーナスの平均額(額面)は以下のようです。
■一般診療所(全体)に所属する医療従事者の賞与平均額
| 職種 | ボーナス(賞与) | 年間の平均給料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 医師 | 33万9575円 | 1085万3589円 (月給90万4466円) | 1119万3164円 |
| 看護職員 | 67万5246円 | 336万9838円 (月給28万820円) | 404万5085円 |
| 医療技術員 | 67万2157円 | 354万1246円 (月給29万5104円) | 421万3403円 |
| 事務職員 | 49万4821円 | 269万954円 (月給22万4246円) | 318万5775円 |
「第24回医療経済実態調査(医療機関等調査)の報告 (令和5年11 月)」をもとにクリニック未来ラボ編集部が集計
※給料には、扶養手当、時間外勤務手当、役付手当、通勤手当など労働の対価として職員に支給したすべてのものが含まれる
※月給は、クリニック未来ラボ編集部が年間の平均給料を12ヵ月で割った金額
※「看護職員」とは、保健師、助産師、看護師、准看護師
※「医療技術員」とは、診療放射線技師、臨床検査技師、栄養士、理学療法士、作業療法士など医療に関わる専門技術員
全国平均のデータであるため、すべてのケースに当てはまるとは限りませんが、クリニックに勤務する医療従事者の賞与額には一定の傾向が見られます。
年間の平均給料を12ヵ月で割ったものを月給とした場合、年間賞与は以下のような水準となっています。
- 看護職員:約2.4ヵ月分(67万5246円)
- 医療技術員:約2.3ヵ月分(67万2157円)
- 事務職員:約2.2ヵ月分(49万4821円)
厚生労働省の「令和6年(2024年)賃金構造基本統計調査」(※2)によれば、大企業・中小企業に勤める一般労働者の年間ボーナス額(年間賞与その他特別給与額)の平均は95万4700円です。これと比較すると、クリニックに勤務する医療従事者の賞与はやや低い傾向にあるといえます。
ただし、あくまでもこれらの数値は平均的な賞与額であるため、実際には業務内容や責任の重さ、役職、勤続年数、資格の有無などによっても差があります。
特に、臨床検査技師や診療放射線技師などの医療技術職は、専門資格や経験年数に応じて支給額が上乗せされるケースが多く、スキルアップや資格取得が待遇に反映されやすい職種です。また、医療事務や受付スタッフも、経験や業務範囲によって支給額に幅があり、レセプト業務や管理業務を担う場合は、より高い水準となる可能性があります。
一方、医師については、年俸制契約や成果報酬型の給与体系が導入されていることが多く、ボーナスは少ない傾向にあります。
※1 出典:中央社会保険医療協議会「第24回医療経済実態調査(医療機関等調査)報告 ー令和5年実施ー」(令和5年11 月)
※2 出典:厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」の「一般労働者 産業大分類」の「学歴、年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額の企業規模計(10人以上)」
地域別
地域別に見ると、クリニックのボーナス水準は都道府県によって大きく異なります。
同じく「令和6年(2024年)賃金構造基本統計調査」の看護師データから見ていきましょう。この調査は、クリニックと病院を合わせた統計となっており、また調査の実施年によって順位に変動がありますが、一定の傾向を読み取ることができるはずです。
同調査によれば、都道府県別に集計した看護師の全国平均は、年間賞与が83万5000円、月額給与が36万3500円、年収519万7000円(平均年齢41.2歳)です。
これに対し、ボーナス支給額が高い地域、低い地域は以下のようです。全国トップの大阪府と最下位の沖縄県では、最大で約43万円もの差があります。
■ボーナス支給額が高い地域(上位5位+全国平均)
| 都道府県 | 賞与 | 給与額 | 年収 |
|---|---|---|---|
| 大阪 | 106万8300円 | 37万7500円 | 559万8300円 |
| 岩手 | 105万7900円 | 33万9400円 | 513万700円 |
| 山口 | 98万4400円 | 34万2900円 | 509万9200円 |
| 秋田 | 97万5400円 | 34万6900円 | 513万8200円 |
| 栃木 | 96万6000円 | 35万8900円 | 527万2800円 |
| 全国 | 83万5000円 | 36万3500円 | 519万7000円 |
「令和6年(2024年)賃金構造基本統計調査」の「一般労働者 都道府県別」の「都道府県、職種(特掲)、性別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)」をもとにクリニック未来ラボ編集部が集計
■ボーナス支給額が低い地域(下位5位+全国平均)
| 都道府県 | 賞与額 | 給与額 | 年収 |
|---|---|---|---|
| 沖縄 | 63万1600円 | 31万6900円 | 443万4400円 |
| 鹿児島 | 64万1500円 | 30万2300円 | 426万9100円 |
| 埼玉 | 66万4000円 | 37万800円 | 511万3600円 |
| 福岡 | 68万500円 | 33万6600円 | 471万9700円 |
| 宮崎 | 69万3900円 | 30万3600円 | 433万7100円 |
| 全国 | 83万5000円 | 36万3500円 | 519万7000円 |
「令和6年(2024年)賃金構造基本統計調査」の「一般労働者 都道府県別」の「都道府県、職種(特掲)、性別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)」をもとにクリニック未来ラボ編集部が集計
岩手県では、給与額が全国平均を下回る一方で、賞与額が2位と高く、年収全体では全国平均並みとなっています。一方、沖縄県や鹿児島県では、給与・賞与ともに全国平均を下回っており、年収水準も低めです。
岩手県などのような地方中核都市では、公立・公的病院が地域医療の中心的な役割を担っており、その待遇が地域の医療従事者にとっての基準となることがあります。そのため、クリニックでも看護師などの医療従事者の採用や定着を図る目的で、賞与などの待遇を公的病院の水準に近づけるケースが見られます。
また、大都市圏で見ると、大阪府は給与・賞与ともに全国平均を上回り、年収では全国第3位となっています。一方、東京都や神奈川県では、給与額はそれぞれ全国1位(40万5600円)、3位(38万8900円)と高水準ではあるものの、賞与額は82万1900円、79万5800円と全国平均(83万5000円)を下回っています。
このように、大阪府、京都府などの一部を除き、都市部では月々の給与が高い一方で、賞与は抑えられる傾向にあるようです。
経営形態別
クリニックの開設者が「個人」(医師個人が開設・経営する診療所)か「医療法人」(法人が開設・経営する診療所)かによっても、賞与の水準には違いが見られます。
一般的には、医療法人のほうが賞与水準は高いことが多いです。
その傾向は、同じ「第24回 医療経済実態調査(医療機関等調査)の報告(令和5年11月)」からも読み解くことができます。以下の表は、個人クリニックと医療法人で働く医療従事者の賞与水準を比較したものです。
■一般診療所における開設者別の医療従事者の賞与平均額
| 職種 | 個人経営 | 医療法人 |
|---|---|---|
| 医師 | 117万5728円 | 17万7241円 |
| 看護職員 | 60万339円 | 67万4915円 |
| 医療技術員 | 52万7563円 | 65万697円 |
| 事務職員 | 45万5324円 | 49万574円 |
「第24回医療経済実態調査(医療機関等調査)の報告 (令和5年11 月)」をもとにクリニック未来ラボ編集部が集計
個人クリニックよりも医療法人のほうがボーナス水準は高くなる背景には、いくつかの理由があります。
まず、法人化によって経営基盤が安定しやすくなることが挙げられます。医療法人では複数の診療所を運営しているケースも多く、収益源が分散されるため、経営の安定性が高まります。その結果、人件費(賞与を含む)に予算を割きやすくなります。
さらに、大規模な医療法人では、多くの人材を安定的に確保する必要があることから、待遇面の充実や人事評価制度の整備など、組織としての競争力を重視する傾向があります。
ただし、医師に限って見ると、逆転現象が見られます。個人クリニックの賞与額が117万5728円であるのに対し、医療法人は17万7241円と極端に少なくなっています。
しかし、これは年俸制契約や成果報酬型の給与体系の導入が影響しているものと考えられます。実際、同調査における両者の平均年収を比較すると、医療法人に勤務する医師の平均年収のほうが高くなっています。
- 個人クリニックの医師の平均年収:984万4146円
- 医療法人の医師の平均年収:1118万508円
クリニックのボーナスの決め方
クリニックのボーナス制度は、経営状況や組織体制、スタッフ構成に応じて柔軟な設計が求められます。ボーナスの種類や支給の基準を明確にして、スタッフが納得できる制度を整えることが重要です。
ここでは、ボーナスの種類や支給要件、職種・雇用形態ごとの調整方法を解説します。ボーナス制度は単なる金額の設定にとどまらず、スタッフの貢献度や職場への定着意欲を高める仕組みとして活用するのがポイントです。
ボーナスの種類を検討する
まず、自身のクリニックでどのようなボーナス制度を導入するかを検討しましょう。
クリニックで最も一般的なボーナスの制度は、「基本給連動型賞与(基本給の〇ヵ月分)」として支給する方法です。安定的なボーナスの支給が可能ですが、経営が悪化した場合でも支給義務が生じる可能性があるため、リスク管理が必要です。
その他にも、クリニック全体や個人の業績に応じて支給額を変動させる「業績連動型賞与」や、年度末などに業績が良い場合のみ支給する「決算賞与」などがあります。自院の経営方針や財務状況に合わせて、最適な方法を選びましょう。
支給要件を決定する
ボーナスの支給には明確な要件を設定する必要があります。
一般的には、「勤続半年以上で半額、1年以上で満額」「勤続1年未満は対象外」などのように、在籍期間で基準を設けるクリニックが多いです。また、支給額を基本給や月給に連動させたり、勤怠不良や勤務態度が悪い場合、業績不振の場合には減額・不支給にしたりするクリニックもあります。
「誰に・いくら・なぜ支給するのか」が曖昧な場合、 スタッフから「自分だけ少ないのはなぜ?」といった不満が出たり、 試用期間中や退職予定のスタッフとの間で「ボーナスを支給する/しない」を巡ってもめるなど、 トラブルにつながる可能性があります。
そのため、これらの要件は就業規則や給与規定に明記し、スタッフ全員へ周知することで、トラブル防止につながります。
制度設計の基本を押さえた上で、運用面では査定期間の設定や試用期間中のスタッフへの取り扱い、産休・育休取得者への配慮など、細かなルール作りが求められます。
雇用形態や職種ごとの支給調整(倍率)を検討
クリニックには正職員・契約職員・パート・アルバイトなど多様な雇用形態があります。そのため、それぞれの雇用形態に応じて賞与の支給額を調整するための「倍率」を設定する必要があります。
多くのクリニックでは、正職員には満額(1.0倍)の賞与が支給される一方で、契約職員やパートには支給なし、または寸志程度の支給にとどまるケースが多く、アルバイトには賞与が支給されないのが一般的です。
ただし、2020年4月に施行された「パートタイム・有期雇用労働法」により、同じ業務内容であれば、正職員と同様の待遇(賞与を含む)が求められるようになりました。これを受けて、正職員以外の契約職員やパートタイマーにも、0.5倍~0.8倍程度のボーナスを支給する医療機関もあるようです。
また、業務内容や責任の重さを考慮し、看護師・技師・事務職など職種ごとに支給基準や倍率を変えるケースもあります。さらに、等級や役職、特殊業務や資格手当の有無なども加味し、調整するのが一般的です。これらのさまざまな要因を考慮し、公平性と納得感を意識した制度設計を心がけましょう。
クリニックがボーナスを支給する際の注意点
ボーナス制度はスタッフの満足度や院内の雰囲気に直結するため、運用には細心の注意が必要です。
支給基準が不明瞭だったり、運用に不公平さがあったりすると、スタッフの不満やトラブルの原因になることがあります。ここではボーナス支給時に特に注意すべきポイントをまとめました。
支給要件を明確に設定する
前述したように、ボーナス制度を適切に運用するためには、「誰に・どのような条件で・どれくらいの金額を支給するか」といった支給条件や基準を明確に設定し、就業規則や雇用契約書などに記載しておくことが重要です。
例えば、支給対象となる勤続年数や在籍期間、査定期間、勤務状況、雇用形態、職種・役職・等級、業績評価など、具体的なルールを定めておくことで、スタッフ間に不公平感が生じたり、支給の有無を巡ってもめたりするような事態を防ぐことができます。
また、支給基準や計算方法については、事前にスタッフに対して丁寧に説明し、納得感を高めることも大切です。
ボーナス支給を確約しない
ボーナスの支給は法律上の義務ではないため、業績や経営状況に応じて支給の有無や金額を柔軟に決定できます。しかし、「基本給の〇ヵ月分」などと具体的な支給内容を労働契約書や就業規則に明記すると、経営が悪化した場合でも支給義務が発生するリスクがあります。
そのため、ボーナス支給を安易に確約するのではなく、「業績等により支給しない場合がある」といった文言を明記しておくことが、トラブル回避につながります。
また、求人広告や面接時に過度な期待を持たせないよう、制度の趣旨や支給条件を正確に伝えることも大切です。経営状況や職場環境の変化に柔軟に対応できるよう、制度設計の段階からリスクヘッジを意識しましょう。
金銭的な報酬だけに頼らない
賃金や賞与などの報酬制度は、スタッフの満足度を高める上で重要な要素です。しかし、金銭面に不満があると、安心して長く働き続けることが難しくなる場合があります。
そのため、金銭面だけを充実させるのではなく、職場環境や人間関係、働きがいなどにも目を向けることが大切です。
最近では、教育体制の整備や働きやすい環境づくりに力を入れるクリニックも増えており、人材の定着や診療体制の安定につながる取り組みが進んでいます。報酬制度だけでなく、職場の仕組みや働く人を支える体制も含めて、バランスよく整えることが、持続可能な人材確保の鍵となるでしょう。
評価基準・査定方法を公平にする
賞与は、単なる金銭的報酬ではなく、スタッフの貢献度や勤務態度への評価を「お金で見える化」したものです。評価と報酬が連動することで、組織としての価値観や方針をスタッフに伝える重要な手段となります。
そのため、ボーナスを支給する際には、人事評価制度に基づき、定量的・定性的な目標や評価基準を設定し、透明性と一貫性を持たせることが大切です。評価結果や査定理由が明確になることで、スタッフの評価に対する納得感や満足感を高め、信頼関係の構築、モチベーションや定着率の向上につなげることができます。
ただし、せっかく人事評価制度を導入しても浸透しなければ、スタッフの不満や院内トラブルの原因となる可能性があります。そのため、評価の仕組みを明文化し、全スタッフに周知することを忘れないようにしましょう。
なお、人事評価についての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。
また、人事評価に不安がある場合は、「ドクターズ・ファイル クリニコ」のような、クリニック・医療機関に特化した人事評価システムの活用をするのも手です。
人事評価システムを活用することで、スタッフの貢献度や勤務態度を公正かつ公平に評価できるだけでなく、評価業務にかかる手間や時間を削減することができます。その結果、診察などの他の業務に充てられる時間を増やすことにもつながるはずです。
クリニックへの「人事評価」の導入で
スタッフの生産性向上を実現!
クリニックのボーナスに関するよくある質問(Q&A)
クリニックがボーナス制度を運用する際には、さまざまな疑問や悩みが生じることがあります。
ここでは、クリニック経営者からよく寄せられる質問と、そのポイントをまとめました。実際の運用時の参考として、ぜひご活用ください。
Q.パートスタッフへのボーナスはどうするべき?
法律上、パートスタッフにボーナスを支給する義務はありませんが、就業規則や雇用契約書に記載がある場合は、その内容に従う必要があります。
また、2020年の「パートタイム・有期雇用労働法」施行以降、同じ業務内容であれば正職員と同様の待遇が求められるようになったことから、徐々にパートにも賞与を支給する動きが広がっています。
パートスタッフに賞与を支給する場合は、一律ではなく、勤務日数・勤務時間・貢献度などに応じて金額を調整し、感謝の気持ちとして寸志を金一封(数千円〜数万円)で渡すのが一般的です。また一部のクリニックでは、評価基準を設けて支給するケースも見られます。
パートのモチベーション維持や定着率の向上を図るためには、賞与の支給において柔軟な対応が求められます。
Q.職種ごとにボーナス支給額に差をつけたほうがいい?
業務内容や責任の重さ、資格の有無などに応じて、職種ごとに支給額や倍率を変えるのが一般的です。たとえば看護師と受付スタッフでは、業務の専門性や負担が異なるため、支給額に差をつけることは十分な理由となりえます。
ただし、その差がスタッフの目から見て納得できるものであることが重要です。人事評価制度に基づく明確な基準や評価に対する説明の場を設け、スタッフ間の納得感や公平性を保つように努めましょう。
待遇差が不透明な運用の場合、不満やトラブルの原因になる可能性があるため、職種間の待遇差については定期的な見直しやスタッフからの意見聴取を行うことも有効です。
公平性を保ちつつ、個々の貢献や専門性を正当に評価する仕組みづくりを心がけてください。
Q.小規模なクリニックでもボーナスは設定する?
従業員が5名以下のような小規模なクリニックであっても、経営状況や業績を踏まえ、無理のない範囲で賞与を支給するケースが多いです。なぜなら、賞与の支給は法律上の義務ではありませんが、制度として導入することで、スタッフの満足度向上や職場の安定に大きく寄与するためです。
また、他院との待遇差が求人や定着率に影響する可能性もあり、たとえ少額であっても支給することでスタッフのモチベーションの維持・離職率の低下につながります。
ただし、小規模クリニックでは、業績が安定しないこともあるため、運用の際には、就業規則に「業績によっては支給しないこともある」「勤続年数や勤務態度などを評価基準に含める」などルールを明記することが大切です。
自院の経営状況や採用戦略に合わせて、柔軟に制度設計を行いましょう。
Q.勤続年数が短い人にもボーナスを渡したほうがいい?
多くのクリニックでは、「勤続1年以上のスタッフを対象に支給」「半年以上の勤務で支給額の半額を支給」など、勤続年数に応じて支給する割合を調整する方法を採用しています。
新規採用者や途中入職者など、入職して3ヵ月にも満たないようなスタッフに対しては評価期間が短く、貢献度の判断が難しいことから、支給しないところが多いようです。ただし、中には感謝の気持ちとして金一封を渡すところもあります。
こうした対応については、新規採用者や途中入職者に対して、採用時の説明や契約書で明確にしておくことが重要です。特例措置や例外規定を設ける場合も、全スタッフに周知徹底することで、後々のトラブルを防ぐことができます。
まとめ
クリニックのボーナス制度は、スタッフの士気や定着率に大きく影響します。
制度の内容はクリニックごとに異なるため、ここで紹介した最新データをもとに、職種・地域・経営形態別ごとの相場を把握した上で、自院の経営状況や人材戦略に応じた柔軟な設計が求められます。
制度を運用する際には、支給基準や計算方法を明確にし、就業規則や雇用契約書に記載することで、トラブルの予防につながるでしょう。また、支給要件や評価基準には透明性と公平性を持たせることで、スタッフの納得感を高めることができます。
スタッフが安心して長く働ける職場をつくるためには、経営状況や人材の変化に応じて、現場の声も聞きながら定期的にボーナス制度を見直し、運用改善に取り組んでみてはいかがでしょうか。(クリニック未来ラボ編集部)
◇ ◇ ◇
今回取り上げたスタッフのボーナスをはじめ、人材や組織に関する課題を抱えている場合は、一人で悩まず、専門家の力を借りることも選択肢の一つです。
クリニック向け総合サービスプラットフォーム「ドクターズ・ファイル」が提供する「人事の外来」では、人事(HR)の専門家から、人材採用・育成・評価・組織開発・スタッフとの信頼関係構築などに関するアドバイスを受けることができます。
人事に関するお悩みやご相談がある方は、ぜひ一度「人事の外来」へお問い合わせください。