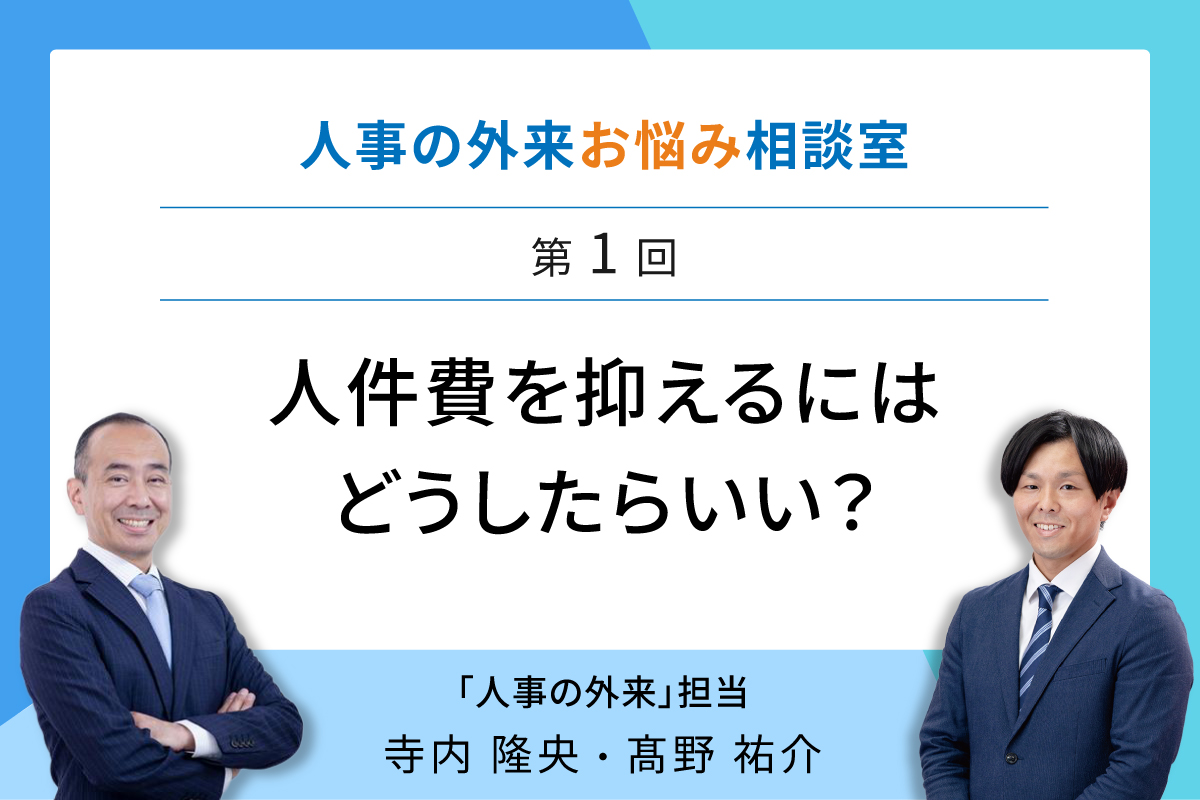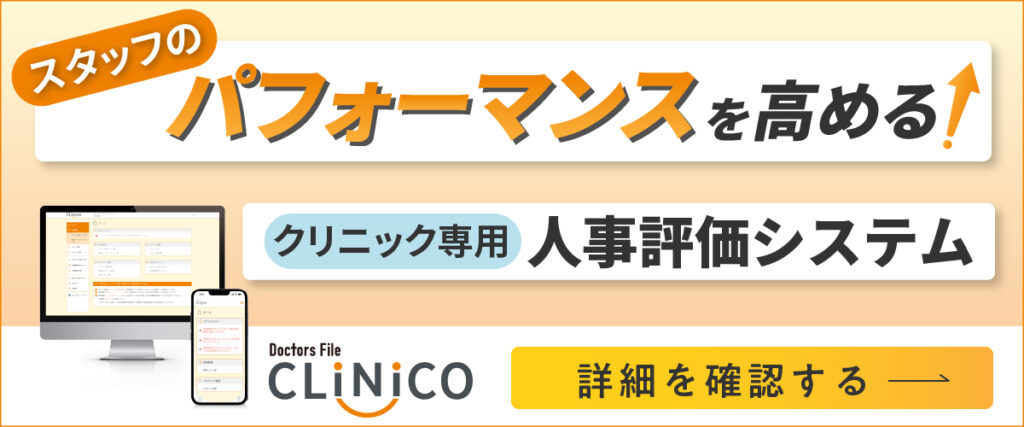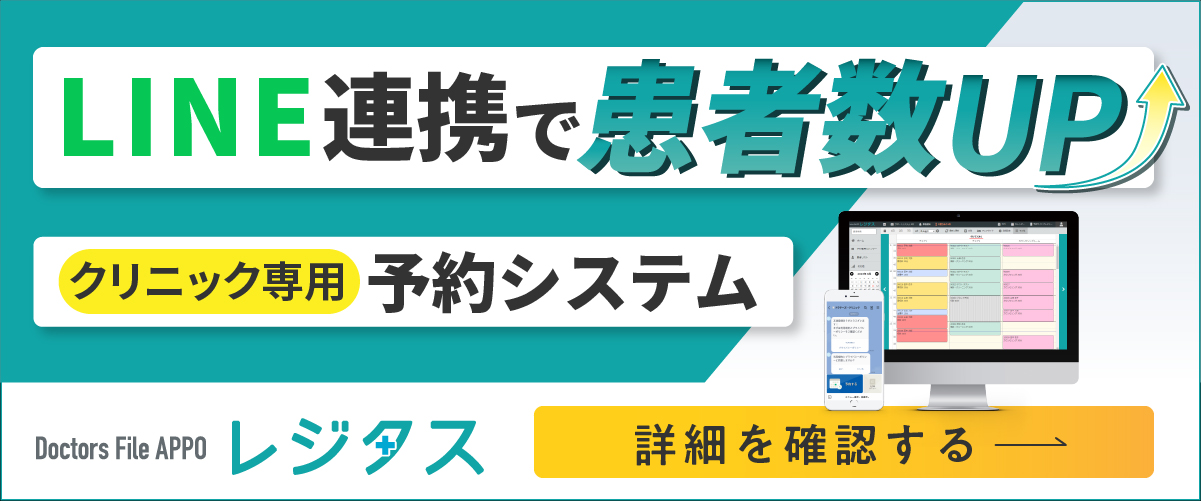人件費率を抑えたいAクリニックのお悩み
今回は、「人件費を抑えたい」「人件費率を下げたい」と思っているAクリニックのお悩みを解決します。
東京都内に開業して10年になる整形外科。理学療法士と作業療法士による丁寧なリハビリを打ち出している。2~3年で辞めるスタッフが多く、都度人員補充をしながら人数をキープ。在籍している6人の理学療法士、2人の作業療法士はいずれも正社員。
人件費に漠然とした不安があり、診療報酬改定の影響も心配
さっそく、Aクリニックから寄せられた悩みを見ていきましょう。
給料の上昇傾向がある中で、このままでやっていけるのか、不安です。2024年度の診療報酬改定でスタッフの賃上げを指摘されたこともあってか、近隣のクリニックでは、一律で昇給しているところもあるし……。
当院は看護師・理学療法士・作業療法士・放射線技師・リハビリ助手・医療事務と、スタッフの職種も人数も多いので、人件費の割合は大きいほうだと思いますが、何%かなどは、あまり計算していません。
収益はここ数年横ばい。人件費を抑えるにはスタッフの給料を下げるべきかとも思ったのですが、今いるスタッフさんに辞められたら困ります。もし退職して新たなスタッフを採用するとしても、給料が安いといい人材に来てもらえないでしょう。なので毎年頑張っているな、と思ったスタッフや、長く勤めてくれているスタッフは昇給しています。そのためじわじわと人件費が上がっています。
税理士さんからは、「もっと人件費率を抑えて」と言われていますが、具体的にどうすればいいのかわかりません。
人件費の基本│人件費率の計算方法は?
クリニックにおける人件費には、スタッフの基本給や賞与、各種手当、退職金のほか、法定福利費、福利厚生費、通勤費、社宅費用など、スタッフに関わるすべての費用が含まれます。
「人件費率」とは、クリニックの総収入に対して人件費がどの程度占めているかを示す割合のこと(売上高人件費率)。
人件費率=人件費÷医業収益高×100
として算出します。このほか、売上総利益(粗利益)をもとにした計算方法もあります。
なお、クリニック未来ラボ編集部が「直近1年の人件費比率」について開業医に調査(※)を行ったところ、「10%以下」が5.8%、「10~20%」が23.2%、「20~30%」が25.0%、「30~40%」が17.4%、「40%以上」が7.0%、「人件費率がわからない」の回答が21.6%という結果に。
2割以上の開業医が人件費率を把握していない実態が明らかになっています。
※「開業医の経営・働き方に関する実態調査」:調査対象/全国の30~90代の医科の開業医500人、調査期間/2024年10月22日(火)~11月11日(月)、調査方法/インターネットでのパネル調査
人件費率の相場とは
無床か有床か、院内処方か院外処方か、といったクリニックの形態や規模、スタッフの人数などによって、人件費率の適正値は異なりますが、一般的には25~30%程度といわれるようです。また、個人クリニックに比べて医療法人のクリニックのほうが、医療スタッフに加え管理・事務スタッフも多く必要であるため、その分、人件費率が上昇すると考えられます。
あくまで参考・目安ですが、厚生労働省が実施した「第24回医療経済実態調査(医療機関等調査)」によると、令和4年の個人クリニックの人件費率は以下の通りです。
| 一般診療所(個人) | |
|---|---|
| 全体平均 | 25.0% |
| 入院診療収益あり | 31.3% |
| 入院診療収益なし | 24.6% |
人件費率を抑えるために気をつけたいタブー6選
医業収益高に対する人件費率を抑えるにあたって、「やってはいけない」と考えられる、気をつけたいことがあります。ここでは6つ紹介します。
給料設定にロジックがない
給料額は人件費に直結します。明確な昇給基準などを設けずに給料額を設定してしまうと、人件費が膨らみ、想定外に人件費率が高くなってしまうことも。給料額は「年齢や経験年数などをもとに算出した基本給+資格手当・役職手当」が基本。また、地域の賃金水準や診療科目の特性なども考慮に入れ、総合的な判断を行うことが重要です。
賞与(ボーナス)が売上高に連動していない
一般企業では、賞与(ボーナス)額は会社全体の業績に比例しますが、クリニックでは、基本給の2ヵ月分など、固定で支給しているケースが少なくありません。業績が良いときは良いのですが、業績が落ち込んでいるにも関わらず、同水準の賞与にし続けると、当然人件費率は上がります。
賞与額は必ずしも固定にする必要はありませんし、賞与ではなくインセンティブ(歩合制報酬)を導入するなど、柔軟な発想で賞与を見直しましょう。
パート・アルバイト職の導入を検討していない
パートやアルバイト、派遣社員を活用することで、人件費を抑えつつ必要な業務を効率良くカバーできます。診療時間や患者の数に応じて柔軟なシフトを組むことで、過剰な人員配置を避けながら、人材を効果的に活用できるでしょう。また、正職員を採用するよりも社会保険料などの負担を軽減できるメリットもあります。
スタッフ採用をする際は、本当に正職員でないといけないのかを念頭に置いて検討することが大切です。
全業務を雇用スタッフが担当しなくてはいけないと決めつけている
クリニックの業務の一部をアウトソーシングすることで、効果的に人件費を削減できるケースが多くあります。
例えば、診療報酬請求やクラーク業務、受付・会計業務、清掃などの業務を外部に委託すれば、スタッフの雇用人数を抑えられます。結果として、雇用に伴う教育コストや社会保険料を削減できます。またスタッフの業務負担を軽減し、コア業務に集中できる点もメリットといえます。
すべての領域の業務を「クリニックのスタッフがやらなくてはいけない」と思い込まず、業務内容によっては、アウトソーシングを活用することを検討してみましょう。
DX化による業務効率向上を考えていない
クリニックの業務効率を大幅に向上させる方法の一つであるDX化。例えば、予約管理システムや電子カルテを導入することで、少人数のスタッフでも効率良く業務を遂行できますし、オンライン予約のシステムを導入すれば、受付業務の負担を大幅に減らすことが可能です。
業務負担が軽減されれば、必要な人員も最小限に抑えられ、人件費の削減につながります。ただし、DX化を進めているからとやみくもに人員を削減するのは、残されたスタッフのモチベーション低下など危険が伴うので要注意です。
システムなどの導入の初期費用・ランニングコストや、始めることの煩わしさ、苦手意識などの理由からDX化を避けず、作業効率化によって人件費が抑えられることを意識してみるようお勧めします。
人件費の増減にだけ目が行っている
人件費率を抑えるというと「人件費を下げる」ことに目が行きがちですが、人件費率(売上高人件費)は医業収益高を分母とするため、医業収益高(売上高)を上げることも重要です。医業売上高を増やすには、集患や、自由診療の適切な設定などの方法があります。
Aクリニックの人件費率の抑え方を専門家がアドバイス
「人事の外来」として数多くのクリニックへ向き合ってきた専門家の二人が、今回Aクリニックから寄せられたお悩みの「人件費率を抑えるにはどうしたらいいか?」について詳しく解説します。
医院の原資に対して人件費が適切かどうかを考える
寺内:まず、人件費の見直しや人件費を抑えることの前提として、「原資を考える」という発想が大事だと思います。医院の給料の原資や賞与(ボーナス)の原資に対して適正配分する、というのが健全な経営といえますね。
髙野:そうですね。Aクリニックさんは、これまで「自院の人件費率が何%かあまり気にしていなかった」とのことですが、給料や賞与を設定する際には、「Aクリニックの原資に対して適切か(多すぎないか、少なすぎないか)」という点を意識すると良いのではないでしょうか。
寺内:以前、あるクリニックから、「賞与は毎年『2ヵ月分』と決めている。収益によって賞与額を変えていない」という話を聞いたことがあります。Aクリニックさんも近しい方法をとっているかもしれませんが、これでは人件費率が適正かどうかはわかりません。
例えば一般企業では、賞与は業績に連動して決め、利益の内一定の割合を「賞与原資」とするケースが多いです。その賞与の原資の中で、評価に応じた適切な賞与額をスタッフごとに定めたり、一律で「〇ヵ月分」と決めたりします。あくまで「賞与の原資」が前提にあっての設定です。
給料も同様に、「給料の原資」が前提にあった上で決めるので、大幅に人件費が増えたり、人件費率が偏ったりすることは少ないのです。このように「原資の設定」を定めることが人件費率を抑える第一歩といえるかもしれません。
昇給を正当な評価で行う
髙野:人件費や人件費率を考える上で、スタッフ一人ひとりの給料額は重要項目です。毎月の給料額を上げる「昇給」は、人件費率に大きく影響します。
そのため昇給をする際は、先述の「給料の原資」を前提にしながら考えていきます。Aクリニックさんは「頑張っている人や長く勤めている人を評価して昇給させている」とのことですが、それはお勧めできません。
給料額を決める上では、「頑張っていると思う」のような主観的な評価ではなく、「明確な評価制度をもとにした適切な評価」をすることが欠かせません。昇給制度を設けているのであれば、明確な評価制度を設けたり定期的なフィードバックを行ったりして、スタッフの努力や実力を客観的に評価し、報酬に反映させるようにしましょう。
これは2つの理由から、人件費率の適切化につながります。
急激な人件費率の上昇を抑えられる
寺内:主観的に昇給させると、「気がついたら人件費がかさんで、人件費率が上がっていた」ということになりかねません。正当な評価と原資の考えは、人件費を「適切にする」ことにつながります。
生産性の向上やスタッフの定着率向上につながる
寺内:Aクリニックさんは、「給料を上げないとスタッフのモチベーションが保てない、辞めてしまう」とお困りとのこと。モチベーションのために、給料原資を超えてでも給料額を上げたり、賞与原資以上の賞与を出したりしなくてはいけないと思っているかもしれません。しかし、スタッフのモチベーションを決めるのは給料額だけではありません。
髙野:実は正当な評価をすること自体、スタッフのモチベーションを上げる方法の一つです。同じ職種でも年次や経験、スキルによってできることが違うので、それぞれのレベルにあった目標を決めて、それをもとに評価するというようなシステムであれば、自己成長が実感できるし、モチベーションを保って働けるのではないでしょうか。
結果的に、原資を越えるほどの給料を出さなくても、スタッフの定着を保つことにつながるケースは多々あります。
スタッフを雇う際にはパート・アルバイト職の検討を
髙野:例えば、正職員(フルタイム勤務)の理学療法士1人分の欠員が出たとき、パート・アルバイト職2人に分割できないかを検討してみてください。
1人当たり勤務時間を短く抑えられて、社会保険料を削減できます。昼休憩のタイミングで1人ずつ配置すれば、休憩時間のロスも少なく済みます。パート・アルバイト職のスタッフを午前と午後でシフト制で配置して、過剰人員にならないようぴったりに入れるような形にできたら、より効率的ですよね。
寺内:「午後はお子さんがいて働けないので、午前だけ働きたい」「午前中は別のアルバイトがあって、午後だけ働きたい」という看護師にとってぴたりとはまる就業時間。特に子育て中の看護師にとっては、午前だけ・午後だけという条件は魅力的ですから、人手不足対策にも効果的ではないでしょうか。
一方、スタッフ同士が顔を合わせる頻度が減るので、コミュニケーション齟齬が生まれやすくデメリットも。より密な連携が必要になりますね。
シフト制の伝達漏れ・ミスを解消!
情報共有アプリで働きやすい職場環境を構築
アウトソーシングで業務効率化
髙野:話を聞いていくと、Aクリニックでは、すべての業務をクリニックのスタッフの中で行っているということでした。もしかしたら、業務領域によってはアウトソーシング化することで、人件費が抑えられるかもしれません。
診療報酬請求やクラーク業務、受付・会計業務、清掃などの業務は外部委託しやすいため、業務量などを加味して活用すれば、雇用人数を抑えられます。「外部委託費がかさむだけじゃないか」と思われるかもしれませんが、スタッフを採用すると、毎月の賃金がかかるだけでなく、教育コストや、社会保険料、賞与を設定している場合はその費用もかかります。外部発注にするとそれらがカットできるため、有効活用したいですね。
電子カルテやオンライン予約システムなどを活用
髙野:電子カルテやオンライン予約システムなどいわゆる「DX化」をすることで、手作業や煩雑な事務業務にかかる時間を削減すれば、限られた人材を有効活用できます。システム導入時や運用の中で費用はかかりますが、アウトソーシング同様、雇用に関わるコストを削減することができます。
寺内:実は人件費の観点だけでなく、医療DXによってスタッフが医療業務に集中できる環境が整って、検査やリハビリをはじめ患者さんに提供するサービスの質が向上したというクリニックも多数ありますよ。
電話応対業務を9割削減!『LINE連携型』の
予約システムで受付業務を効率化
不当解雇や無理な人件費削減にとらわれないように注意
寺内:人件費を落とそうと思ったときに、「現在のスタッフの人数を減らそう」と考えるかもしれませんが、単なる人件費削減のための一方的な解雇は、不当解雇とみなされる可能性があるので絶対にNGです。
また、人件費を削減することだけにとらわれてしまうと、スタッフの離職が増えて日常業務が滞ってしまったり、スタッフのモチベーション低下を招いたり、負のインパクトから、ひいては患者さんの減少につながったりする可能性も。人件費の削減計画は、慎重に、専門家に相談しながら進めることをお勧めします。
Aクリニックの相談Q&A
Q.人件費率が高くなったらスタッフの給料を見直せばよい?
A.それだけでは不十分です。個々のスタッフの人件費を見る前に、「人件費にかかわる原資」が適正かを確認する必要があります。また現状の人件費が適正であるにもかかわらず、業務効率が低い場合もありますから、まずは原資が適正値か、それから、適正配分できているかどうかを見直しましょう。
※クリニック経営における人件費の適正性は「人件費率」「1人当たりの限界利益」「労働分配率」「1人当たりの給与費」「1人当たりの医業収益高」の5つの指標を用いて判断できます。
Q.人件費を抑えるために、スタッフの昇給は慎重になったほうがいい?
A.一度昇給したら、簡単には下げることはできませんから、慎重になったほうがいいといえます。明確な目標設定とそれに対する適切な評価を行うことが大切です。スタッフのモチベーション・満足度のために、昇給だけにとらわれず、インセンティブを導入するなどの工夫も可能です。
Q.人件費率の見直しはどれくらいの頻度ですべき?
A.1~2年に1回が目安です。診療報酬改定の年は、ルールが変わり収益も変化するので、必ず見直したほうがいいと思います。
Q.人件費が高いと、どんなデメリットがクリニックにある?
A.ひとことで言うと、利益の低下です。利益が下がることによって、投資余力がなくなり最新の医療機器を導入することができない、分院を作りたかったけれど作れないなど、理想の医療が実現できないことがデメリットとなるでしょう。
Q.人件費率が高いから人員整理をしたいが、簡単に辞めさせてもいい?
A.絶対にいけません。人件費削減のための一方的な解雇は、不当解雇とみなされる可能性があります。例えば、スタッフ一人ひとりの業務の幅を増やすことで、スムーズにクリニック運営できるようカバーしてもらうなど、人員整理以外の方法を検討してみてください。
Q.ボーナスをなくしたいが、スタッフのモチベーション維持に影響はない?
A.基本給の2ヵ月分など、ボーナスを固定で支給しているクリニックが多いですが、必ずしも固定にする必要はありません。またボーナスではなくインセンティブを導入するなども一つの手段ですので、柔軟に考えましょう。
ただし、今まで支給していたボーナスをいきなりゼロにするというのは、スタッフからの反発を招く可能性があるので注意が必要です。お金だけでスタッフのモチベーションを維持しようとするのは危険だといえるでしょう。
Q.限界まで人件費を抑えているが、人件費率が下がらないのはどうして?
A.人件費を下げるだけでなく、売り上げ(収益)を上げることも重要です。ミスなく正しい診療報酬請求を徹底しましょう。健全な経営を実現するには、経営のプロの視点で客観的に見てもらうことも重要。一人で悩まず、専門家に相談しましょう。
まとめ
クリニック経営において、人件費や人件費率は非常に重要なものです。しかし、日々診療に忙しくしながら、スタッフの給料設定や、それに付随した評価、コミュニケーション、マネジメントについて考えるのは大変なもの。
もしそういったお悩みがあれば、専門家を頼るのも一手です。人材や組織のお悩みがあれば、ぜひクリニック向け総合サービスプラットフォーム「ドクターズ・ファイル」が提供する「人事の外来」のような、人材採用や育成、評価、組織開発、スタッフとの信頼関係の構築へのアドバイスが受けられるサービスを活用してみてください。