クリニックの離職率の現状と業界比較
クリニック経営において、看護師や受付、医療事務などスタッフの離職は採用コストや業務継続性に直接影響する重要な経営課題です。ここでは、医療・福祉業界における離職率の現状と他の産業・業界との比較を中心に解説します。
医療・福祉業界の離職率は本当に高い?
まずは厚生労働省が公表した「令和6年雇用動向調査結果の概況」(※)をもとに、医療・福祉業界の離職率を見ていきましょう。
この調査の対象には、介護サービスなどを提供する福祉分野に加え、病院などクリニック以外の医療機関も含まれています。そのため、クリニック単体の離職率が明示されているわけではありませんが、一定の傾向を読み取ることができるはずです。
同調査によると、2024年(令和6年)の「医療・福祉業界」の離職率は13.8%で、全産業平均の14.2%とほぼ同水準、わずかに下回る結果となっています。
人材不足や厳しい職場環境を背景に、メディア報道などで離職率の高さが強調されがちな医療・福祉業界ですが、実際の離職率はそこまで突出して高いわけではないことが読み取れます。
とはいえ、1年間で約7人に1人が退職する計算となり、これは医療経営にとって大きな課題です。
また、採用と離職のバランスを示す「入職超過率」にも注目すべきです。これは、新しく入ってくる人の数が、辞める人の数をどれだけ上回っているかを示す指標です。全産業の平均の入職超過率が「+0.6%」であるのに対し、医療・福祉業界は「+0.3%」とわずかに低く、医療業界でも人材は確保できているものの、定着しにくい傾向があることがわかります。
このことからも、人材の定着に向けた取り組みが不可欠であると言えるでしょう。
他業界と比較した医療・福祉業界の離職率
同じ「令和6年雇用動向調査結果の概況」によると、2024年(令和6年)における産業別の離職率ランキングは以下のようです。
2024年の離職率が高い産業トップ5
| 順位 | 産業 | 離職率 |
|---|---|---|
| 1位 | 宿泊業、飲食サービス業 | 25.1% |
| 2位 | サービス業(他に分類されないもの) | 20.3% |
| 3位 | 生活関連サービス業、娯楽業 | 19.0% |
| 4位 | 卸売業、小売業 | 15.1% |
| 5位 | 医療、福祉 | 13.8% |
| 全産業 | 14.2% |
厚生労働省「令和6年雇用動向調査結果の概況」の「表4-2産業、就業形態別入職率・離職率・入職超過率(令和6年(2024))」 より一部抜粋
16の産業の中で「宿泊業・飲食サービス業」(25.1%)が最も離職率が高く、サービス業全般で見てもその傾向が見られます。
一方で、「医療・福祉」(13.8%)は、離職率上位ランキングの5番目に位置しています。全産業の平均(14.2%)よりも離職率がやや下回っているとはいえ、他業界と比較して決して定着率が高いとは言い難い状況です。
看護師の離職率
スタッフの中でも、特に看護師はクリニック経営において欠かせない存在です。ここでは離職率がどれほどなのか、具体的な数値をもとに見ていきます。
取り上げるのは、日本看護師協会が毎年、全国の病院を対象に実施している「病院看護実態調査」です。この調査の対象にクリニック(診療所)は含まれませんが、病院勤務の看護師の離職率から、一定の傾向や課題が見えてくるはずです。
看護師と一般労働者との比較
2025年発表の「2024年 病院看護実態調査 報告書」(※1)によれば、2023年度における看護師の離職率は、以下の表のようです。
| 区分 | 離職率(%) |
|---|---|
| 正規雇用看護職員(全体) | 11.3 |
| 新卒採用看護職員 | 8.8 |
| 既卒採用看護職員 | 16.1 |
日本看護師協会「2024年 病院看護実態調査 報告書」より一部抜粋
同調査によれば、2023年度における正規雇用の看護職員(新卒採用者や既卒採用者を含む)の離職率は11.3%でした。
一方、厚生労働省の「令和5年雇用動向調査結果の概況」(※2)によれば、2023年(令和5年)における一般労働者の離職率は12.1%であり、正規雇用の看護職員の離職率はこれとほぼ同水準、わずかに上回る結果となっています。なお、ここでいう一般労働者とは全産業における、短時間労働者(パートタイム)以外の常用労働者を指します。
両調査は前提条件が異なるため厳密な比較とはいえませんが、離職率の傾向を捉える手がかりにはなるでしょう。
看護師の離職率は、一般労働者と大きな差はありません。しかし採用区分別に見ると、既卒採用の離職率は16.1%と高く、新卒採用(8.8%)の約1.8倍に達しています。
このことから、新卒採用は辞めにくい一方で、既卒採用は過去の職場での経験やライフステージの変化、キャリア志向の明確化などを背景に、職場選びに対してより厳しい視点を持っていることがうかがえます。
看護師の離職率が高い都道府県・低い都道府県
次に、地域ごとの離職率に注目し、正規雇用の看護職員について、離職率が高い・低い都道府県の上位5つを表にまとめました。
■離職率が高い都道府県 トップ5位(正規雇用看護職員・2023年度)
| 都道府県 | 離職率(%) | |
|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 14.2 |
| 2位 | 大阪府 | 13.7 |
| 3位 | 神奈川県 | 13.6 |
| 4位 | 兵庫県 | 13.1 |
| 5位 | 鹿児島県 | 13.0 |
日本看護師協会「2024年 病院看護実態調査 報告書」より一部抜粋
■離職率が低い都道府県 トップ5位(正規雇用看護職員・2023年度)
| 都道府県 | 離職率(%) | |
|---|---|---|
| 1位 | 岩手県 | 6.8 |
| 1位 | 山形県 | 6.8 |
| 3位 | 秋田県 | 7.4 |
| 4位 | 富山県 | 7.6 |
| 5位 | 徳島県 | 7.9 |
日本看護師協会「2024年 病院看護実態調査 報告書」より一部抜粋
都市部(東京・大阪・神奈川)では離職率が高く、東北・北陸・四国などの地方では低い傾向が見て取れます。
この背景の一つには、病院や診療所が人口の多い都市部に集中しており、都市部では転職先の選択肢が豊富で、離職後も比較的容易に再就職できる環境が整っていることが推察されます。
※1 出典:日本看護協会「2024年 病院看護実態調査 報告書」
※2 出典:厚生労働省「令和5年雇用動向調査結果の概況」
クリニックで離職につながりやすい8つの原因
クリニックの離職率を改善するには、業界特有の事情と、運営面での課題の両方に向き合う必要があります。ここでは、離職率が高い以下8つの原因を解説します。
1. 過重な業務量と時間外労働
クリニックでスタッフの離職率が高くなる要因の一つに、過重な業務量と時間外労働があります。病院勤務のような夜勤はないものの、クリニックは少人数体制であるため、一人ひとりの業務負担が大きくなりがちです。
例えば看護師の場合、看護業務に加えて、状況によっては受付対応や会計補助、清掃などを兼務することもあり、役割の幅広さが負担につながることがあります。
特に人手不足のクリニックでは、一人あたりの業務量が増え、診療時間外の片付けや書類作成、レセプト業務、患者対応などで残業が常態化するケースも少なくありません。こうした状況が続くと、スタッフは心身ともに疲弊し、健康を損なうリスクが高まります。その結果、離職を選ぶスタッフが増えてしまうのです。
さらに、人員不足による業務過多は、新たな離職を招き、結果として人員不足が深刻化するという悪循環に陥ることもあります。この悪循環を放置すれば、残ったスタッフへの負担が一層増し、クリニック全体のサービス品質低下にもつながります。
2. ワークライフバランスの悪さ
クリニックは日勤中心の勤務が可能なため、一般的には病院と比べるとワークライフバランスを取りやすい職場とされています。しかし、すべてのクリニックが理想的な環境とは限りません。
限られた人員で対応していることから、急な欠勤や繁忙期にはシフト調整が難しく、休日出勤や残業が発生することもあります。また現場によっては、有給休暇が取りにくい、柔軟な勤務体制が十分に整っていないといった課題が見られることもあるようです。
特に、育児や家庭との両立を希望するスタッフにとっては、大きな負担となり、離職につながる可能性があります。
3. 職場の人間関係の問題
クリニックでは限られた人数でチームを構成するため、良くも悪くも職場の人間関係がスタッフの離職に与える影響は非常に大きくなります。特に以下のような問題が起こりやすい傾向があります。
- 院長や上司との関係がうまくいかない
- 同僚とのコミュニケーション不足や対立が生じる
- パワハラやセクハラなどのハラスメントの問題がある
- 教育・指導の方法が不適切で、成長を実感しづらい
問題が生じても相談できる相手が限られているため、悩みを抱えたまま働き続けるケースも少なくありません。こうした人間関係の問題は、チーム全体の雰囲気や業務の質にも悪影響を及ぼし、スタッフのモチベーション低下や退職の原因にもなりかねません。
4. 待遇面の不満(給与・福利厚生)
クリニックスタッフの離職理由として、待遇面への不満は非常に大きな要因です。特に給与水準が周辺の医療機関と比べて低い、業務量に対して報酬が見合っていないと感じると、モチベーションの低下や転職の検討につながります。
また、昇給や賞与の基準が不透明だったり、交通費・住宅手当・休暇制度・健康診断・メンタルケアなどの支援が不十分だったりする場合も、不満の要因となりやすいです。
もちろん、お金だけが働く目的ではないというスタッフも多くいますが、待遇への不満は日々の業務の中で蓄積されやすく、離職の引き金になりやすいのも事実です。
待遇面の課題は定着率に直結するため、制度整備が後回しになっている、定期的な見直しがされていないクリニックは、改善が求められます。
5. 医療特有の閉鎖的環境とストレス
クリニックは少人数で協力しながら運営していることが多く、比較的閉鎖的な環境といえます。そのため、同じメンバーと長時間過ごす中で、些細な対立や不満が大きなストレスに発展しやすい傾向があります。
こうした環境下では、医療従事者は特有の精神的負担にさらされやすくなります。主なストレス要因には、患者の健康や安全に関わる責任の重さ、医療ミスへの不安、さらにクレーム対応などによる心理的プレッシャーが挙げられます。
また、業務の分担が曖昧で「何でも屋」になりがちな点や、相談できる相手が限られていることも、ストレスを蓄積させる要因となります。このようなストレスが長期間続くと、バーンアウト(燃え尽き症候群)を引き起こし、結果的に離職につながるケースも少なくありません。
6. キャリア成長の機会不足
キャリア成長の機会が限られているクリニックでは、将来への不安や物足りなさを感じる医療従事者も少なくありません。
クリニックは病院と比べて診療科や業務の幅が狭く、昇進ポジションも少ないため、専門性を高めたい医療従事者にとっては物足りなさを感じることもあるようです。
こうした環境が、将来のキャリアに不安を抱かせ、離職の一因となることもあります。特に以下のような点が課題として挙げられます。
- 研修や学会参加のための時間的・金銭的支援の不足
- 専門的なスキルを習得する機会の制限
- キャリアパスの不明確さ
- 昇進や昇給の基準が不透明
日々の業務がルーチン化しやすく、将来の展望が描きづらい環境では、向上心の高いスタッフほど「もっと学べる職場」「専門性を高められる環境」を求めて転職を考えるようになります。
7. 設備・システムの不備による業務非効率
古い医療設備や非効率なシステムは、スタッフの業務負担を増やし、日々のストレスや不満の原因となることがあります。特に以下のような課題が挙げられます。
- 医療機器の老朽化
- 業務効率化ツールの不足・欠如
例えば、予約管理システムや自動精算機、電子カルテ、Web問診などのツールは、スタッフの作業をスムーズに進める上で有用です。近年では、こうしたツールを導入するクリニックも増えており、未整備の環境では手作業が多くなるため、「非効率」と感じる場面が増える傾向にあります。
もちろん、患者層や診療方針に合わないツールを無理に導入したり、コスト面からもすべての最新設備をそろえたりする必要はありません。しかし、業務の煩雑さやストレスが蓄積されることで、「働きづらさ」を感じ、離職を検討する要因となる可能性がある点には注意が必要です。
8. 教育・指導体制の不足
新人スタッフの早期離職には、教育・指導体制の不備が一因となっているケースも少なくありません。入職直後は誰でも不安を感じるものですが、サポートが不十分だと孤立感や無力感につながりやすくなります。
クリニックでは専門性の高い業務が多く、一つのミスが患者の安全に直結します。だからこそ、「すぐに質問できる」「失敗してもフォローがある」といった安心できる環境づくりが重要です。
主な課題としては、以下のような点が挙げられます。
- 人手不足で教育時間の確保が困難
- 体系的な研修プログラムがない
- 教育担当者がいない、または指導が不十分
- 業務マニュアルが未整備
- OJT(現場での実地指導)に頼りすぎている
学ぶ機会が少なければ、「成長できない」「このままでいいのだろうか」と感じてしまい、やる気の低下や職場を離れるきっかけになることもあります。
クリニックの離職率を下げる6つの方法
クリニックの離職率を下げる方法を6つにまとめました。実践しやすいものから、ぜひ自身のクリニックで導入を検討してみてはいかがでしょうか。
1. 採用時のミスマッチを防ぐ採用基準の明確化
採用段階でのミスマッチを減らすことは、スタッフの離職を防ぐ第一歩となります。
募集内容の準備から面接、試用期間に至るまでの流れの中で、クリニックとしての採用基準(理念・人物像・業務内容など)を明確にし、それを応募者に伝えることが重要です。
具体的な取り組みとしては、以下のような方法が効果的です。
- 職務内容や期待される役割の詳細な説明
- クリニックの理念や方針の共有
- 実際の勤務環境や業務の様子を見学できる機会の提供
- 面接時に現場スタッフとの交流時間を設ける
- 試用期間を活用し、双方が適性を確認できる期間を確保する
こうした工夫により、「思っていた仕事と違った」というギャップを減らし、早期離職の防止に役立ちます。また、クリニックの文化や価値観に合う人材を採用することで、チームの一体感や定着率の向上にもつながります。
2. 労働環境の改善(シフト・休暇・給与・福利厚生)
スタッフの定着率を高めるためには、労働環境の改善も有効な方法の一つです。ワークライフバランスを考慮した勤務体制や、適切な報酬体系を整えることで、スタッフの満足度や職場への信頼感が高まり、離職の抑制につながります。
効果的な労働環境の改善策として、以下のような取り組みが挙げられます。
| 改善策 | 具体例 |
|---|---|
| シフト制度の柔軟化 | 希望休の受付・反映、時短勤務の導入など |
| 適正な人員配置 | 業務量に応じた人員調整、繁忙時間帯に合わせたシフト設計 |
| 給与体系の整備 | 業界水準を参考にした給与設定、昇給ルールの明確化 |
| 社会保険の整備 | 健康保険・厚生年金への加入 |
| 福利厚生の充実 | 健康診断の実施、各種割引制度、住宅手当の導入など |
| 退職金制度の導入 | 共済制度や企業型DC(確定拠出年金)の導入 |
労働環境の改善は「スタッフを大切にする」というクリニックの姿勢を示すものであり、他院との差別化にもつながります。そのような姿勢が評価されることで、働きやすさを重視する優秀な人材も集まりやすくなるはずです。
ただし、これらの施策には一定のコストが伴うため、クリニックの規模や運営方針に応じて、現実性や継続性を踏まえた段階的な導入が望ましいでしょう。
3. 明確な基準設定と透明性のある人事評価
明確な評価基準に基づく透明性のある人事評価は、職場に対する信頼感を高めるのにお勧めです。評価基準が曖昧なままだと、昇給・昇格に対する不公平感や不信感が生まれやすく、離職の原因となることもあります。
職種によって業務ごとの目標や行動指針を具体的に示し、評価の方法やタイミングをスタッフ全員に共有することで、納得感が高まるというメリットがあります。近年では、大規模病院を中心に人事評価制度の導入が進んでおり、クリニックでも関心が高まりつつあります。
また、評価結果はフィードバック面談を通じて伝えることで、スタッフの成長意欲を引き出し、信頼関係の構築にも役立ちます。こうした仕組みが、安心して長く働ける職場づくりの土台となります。
クリニックへの「人事評価」の導入で
スタッフの生産性向上を実現!
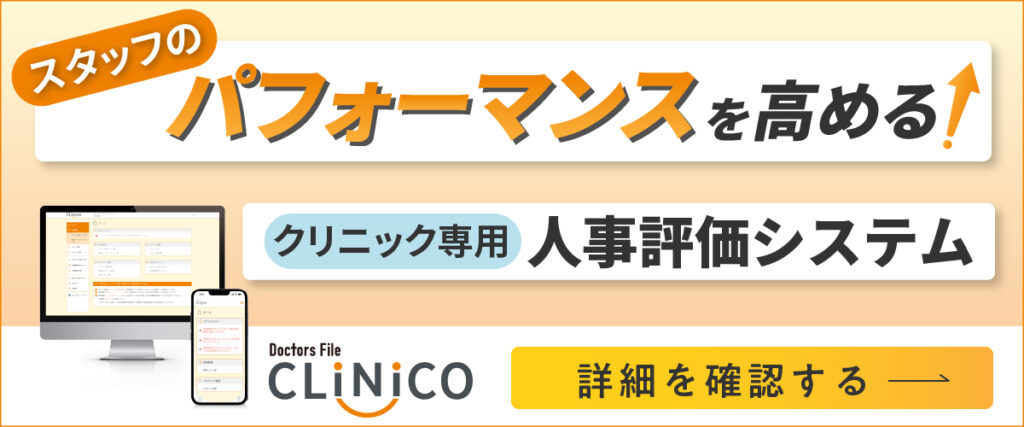
4. 教育体制の構築と成長機会の提供
スタッフの成長を支援する教育体制は、モチベーションの維持と離職防止に大きく貢献します。特に「学び続けられる環境」は、長期的な定着を促す重要な要素です。
効果的な教育体制と成長機会の提供には、以下のような取り組みが有効です。
- 体系的な新人研修プログラムの整備
- 定期的な勉強会やケーススタディの実施
- 外部研修や学会参加のサポート(費用補助・時間確保)
- 資格取得支援(受験料補助・勉強時間の確保)
こうした取り組みは、スタッフの専門性向上だけでなく、「このクリニックで働き続けることで自分も成長できる」という実感を与えます。なお、研修や学会参加は業務への影響も考慮し、年間の上限回数や事前申請ルールなど、現実的な運用ルールを設けることが重要です。
5. 業務効率化のためのシステム導入
スタッフが辞めにくい職場づくりには、業務負担を軽減する工夫も効果的です。患者層や診療方針に応じて、自院に合った適切なシステムやツールを活用することで、働きやすさの向上が期待できます。
例えば、以下のような取り組みがあります。
こうした効率化により、スタッフの時間と心に余裕が生まれます。専門性の高い業務に集中できる環境が整うことで、「この職場で続けたい」と思える要因となり、離職率の低下につながります。
ただし、前述のとおり導入には一定のコストがかかるほか、現場の理解と協力も不可欠です。導入にあたっては、スタッフの声を丁寧に拾いながら、慎重に進めることが重要です。
シフト制の伝達漏れ・ミスを解消!
情報共有アプリで働きやすい職場環境を構築

6. 心理的安全性を高めるコミュニケーション環境の整備
心理的安全性とは、チーム内で自分の意見を安心して述べられる状態のことです。否定されたり、評価が下がったりする不安(=対人リスク)を感じずに発言できる環境が整っていることを指します。
医療現場は職種ごとに役割と権限が異なることから上下関係が生まれやすいものですが、この心理的安全性が高い職場では、スタッフが萎縮せずに発言し、積極的に業務に取り組むことができます。
心理的安全性を高めるための具体策として、以下のような取り組みが有効です。
- チームミーティングでの意見交換の奨励
- 定期的な1on1面談の実施
- 失敗を非難せず、学びの機会として捉える文化の醸成
- 上下関係に縛られないアイデア提案の仕組み
- ハラスメント防止の明確なポリシー策定
下の立場のスタッフが意見を言いにくい雰囲気を改善し、すべてのスタッフが尊重され、自由に意見を述べられる環境を整えることが、チームの一体感を高めます。これは離職防止だけでなく、医療安全や業務改善を支える上でも重要な基盤となります。
まとめ
この記事では、医療業界における離職率の現状、離職につながる要因、そして離職率を下げるための具体的な対策について解説しました。
人材の定着は、クリニックの安定経営と質の高い医療の両立に欠かせません。スタッフが長く働き続けているクリニックは、患者にとっても安心感があり、信頼につながります。
そのためには、採用基準の明確化、教育体制の整備、業務効率化、心理的安全性を意識したコミュニケーションなど、多角的な取り組みが求められます。
スタッフが安心して働ける環境になっているかどうか、今一度、院内の様子を振り返ってみるのもよいでしょう。ちょっとした改善が、定着率アップにつながる一歩になるはずです。(クリニック未来ラボ編集部)
◇ ◇ ◇
今回取り上げたスタッフの離職率をはじめ、人材や組織に関する課題を抱えている場合は、一人で悩まず、専門家の力を借りることも選択肢の一つです。
クリニック向け総合サービスプラットフォーム「ドクターズ・ファイル」が提供する「人事の外来」では、人事(HR)の専門家から、人材採用・育成・評価・組織開発・スタッフとの信頼関係構築などに関するアドバイスを受けることができます。
人事に関するお悩みやご相談がある方は、ぜひ一度「人事の外来」へお問い合わせください。
<執筆者プロフィール>
クリニック未来ラボ編集部
クリニック未来ラボは、開業医、開業を目指す勤務医・医学生に向けたクリニック経営支援メディアです。独自の視線で調査・研究し、より良い医院経営に役立つ情報として発信。「開業医白書」をはじめ、診療報酬改定や医師の働き方改革、医療従事者の転職動向など、医院経営に関する調査レポートも公開しています。

