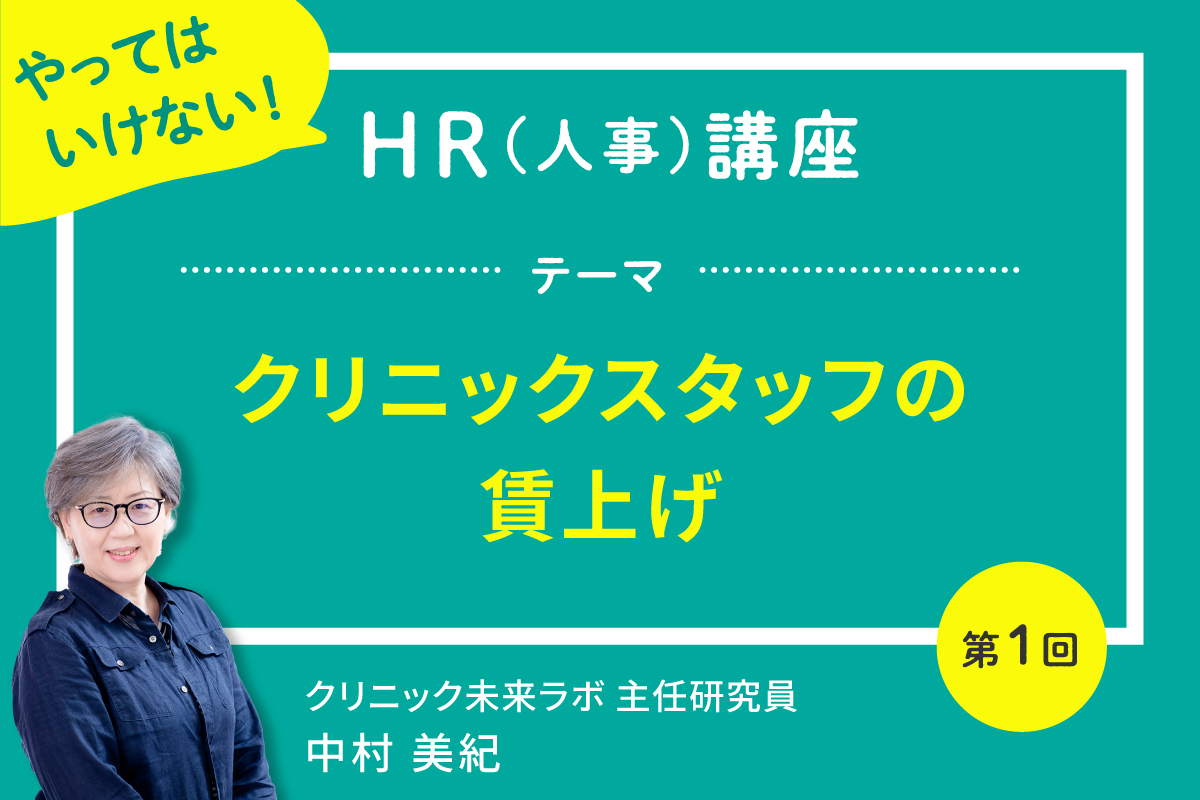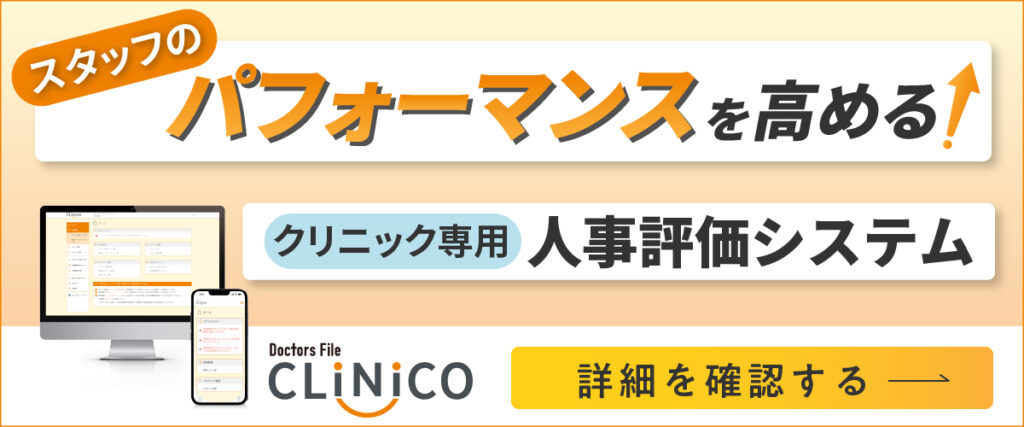クリニックの賃上げとは?
「賃上げ」とは、企業が従業員(スタッフ)の給与を上げることです。
賃上げの方法は大きく2種類、企業が定める規定に基づき年齢や勤続年数・評価などに応じて定期的に昇給する「定期昇給(定昇)」と、従業員の基本給を一律に引き上げる「ベースアップ(ベア)」があります。
賃上げの目的は、従業員に対する仕事への期待を示すことでモチベーションを高め、離職率の低下や優秀な人材の確保につなげることにあります。こうした効果は、結果的にクリニックの持続的な成長を支える重要な原動力となります。
ここ数年、物価上昇による実質賃金の低下や、人手不足による優秀な人材の流出などを背景に、賃上げは全国的に注目されており、2022年以降、大企業を中心に新卒の初任給の引き上げを発表するなど、賃上げが活発化しています。
国は2025年度の最低賃金について、全国平均で過去最大となる時給63円の引き上げを目安として掲げており、すべての都道府県で最低賃金が1,000円を超える見込みです。
一方で、クリニックでも同様に賃上げへの関心は年々、高まっていますが、他業界に比べると医療従事者の処遇改善は遅れているといわれています。
なぜ今、クリニックで「スタッフの賃上げ」が注目されるのか?
他業界に比べて賃上げのペースが緩やかな医療業界ですが、近年は国が主導で推進する令和6年(2024年)度診療報酬改定の影響により、クリニック経営者にとっても「スタッフの賃上げ」を意識せざるを得ない状況となっています。
厚生労働省は2024年度診療報酬改定において、看護師や保健師など医療従事者の人材確保と処遇改善を重要なテーマと位置付け、医療従事者の賃金改善を目的として「ベースアップ評価料」(医療機関が受け取る診療報酬の一部を、医療従事者の賃上げに充てるための制度)の新設などを行いました。
しかし、診療報酬改定に限らず、自主的な賃上げにおいても、固定費の増加は利益を圧迫する可能性があるため、どのように賃上げを進めていけばいいか、頭を悩ませている開業医も少なくないようです。
クリニックの「スタッフの賃上げ」でやってはいけないこと
クリニックスタッフに対して院長自身が賃上げ幅を決める場合、注意しなければいけないことがあります。
クリニックの人手不足の改善策として、賃上げは有用な施策の一つです。実際、クリニック未来ラボ編集部が開業医を対象に調査した「開業医白書2024」(※)でも、「スタッフを定着させるための工夫とは?」という質問に対し、50.0%(1位)もの開業医が「賃金の向上」と回答しています。
しかし、「スタッフの賃上げ」=「給与を上げるだけ」では十分ではありません。あくまでも賃上げは手段であり、本来の目的は従業員のモチベーション向上や人材定着です。
院長が給与を上げることだけに集中してしまうと、次のような「やってはいけない行動」を起こしやすくなるため、注意が必要です。
■やってはいけない!失敗行動の例
1. 人材課題の解決策が“賃上げ頼み”になっている
2. 賃上げに至る評価基準が明確でない
3. 賃上げの目的・理由を説明していない
いずれの行動もスタッフの不信感を招き、職場の信頼関係に悪い影響を及ぼしかねません。
賃上げの本来の目的は、単なる給与調整ではなく、人材への投資であり、能力やスキルの向上を通じて生産性や組織の価値を高めることにあります。自律性が育まれれば、指示がなくても自ら考え行動する力が発揮され、人的資源としての価値はさらに高まります。今はまさに、人材にどう投資し、どう育てるかが問われる時代です。
せっかくの賃上げが、ただ給与を上げるだけで意味を持たせられていないとしたら、早めの改善が必要です。次で、NGな行動を詳しく見ていきましょう。
※「開業医白書2024」:調査対象/全国の30~90代の医科の開業医500人、調査期間/2024年10月22日(火)~11月11日(月)、調査方法/インターネットでのパネル調査
クリニックがやってはいけない「スタッフの賃上げ」3つの失敗行動
ここからは、「スタッフの賃上げ」で陥りやすいNGな行動を詳しく解説します。
1.人材課題の解決策が“賃上げ頼み”になっている
院長が「給与を上げれば大丈夫」と思い込み、ただ賃上げを行ってしまっている場合、短期的にはスタッフ定着において効果があるように見えても、長期的には逆効果になる可能性があります。
なぜなら、お金だけでスタッフの満足度や定着率を高めるのは困難だからです。
しかも、人件費の増加はクリニックの収益を圧迫する可能性があるため、賃上げには限界があります。
もちろんお金は大事ですが、それだけでなく、多くの人は正当な評価や働きがい、成長の機会が、仕事のモチベーションのもとになっています。
「どこを評価されて、なぜ給与が上がったのか」という根拠がわからない状態では、スタッフに納得感を与えられず、職場の不信感や離職リスクを増加させてしまいます。
2.賃上げに至る評価基準が明確でない
評価基準が不透明な場合、「自分の頑張りが給与に反映されない」「あの人の昇給額のほうが高くて公正じゃない」などと、スタッフの不満の種となりがちです。
せっかく賃上げしても、院長の主観や偏見に基づく評価だとして判断されてしまい、スタッフから納得感や満足感を得られず、モチベーションの低下、ひいては離職へつながる可能性もあります。
賃上げに紐づく評価基準が明文化できていないクリニックは、できるだけ早めに役割や成果、行動などを具体的に定義し、スタッフ全員に共有する必要があるでしょう。
3.賃上げの目的・理由を説明していない
賃上げを実施したとしても、「なぜ賃上げしたのか」という理由を院長がきちんと直接フィードバックできていない場合、スタッフに喜ばれるどころか、かえって疑念を抱かせてしまう可能性があります。
クリニックの現場では、日々の診療に追われる中で、院長が賃上げした理由をきちんと説明せず、結果だけを伝えるにとどまったり、そもそも何も伝えなかったりするということがあるのではないでしょうか。
そうした場合、スタッフは賃上げの根拠がわからず、「本当に働きぶりを見て評価してくれたのか?」「もっと給与を上げるためには、次にどんな成果を上げればいいのだろう」といった迷いや混乱が生じやすくなってしまい、賃上げの効果が得られません。
賃上げは、「フィードバック面談(上司が部下へ人事評価の結果とその理由を伝え、課題があったら話し合い、めざすクリニック像の共有やスタッフの成長を促す場)」などとセットで実行することが重要です。
クリニックの「スタッフの賃上げ」で失敗行動が発生する要因
スタッフの賃上げでNGな行動が発生する要因は、いくつかあります。
一つには、クリニックの院長は医療分野ではエキスパートである一方、「経営や人材育成にはあまり自信がない」「賃上げに関わる業務に十分な時間が割けない」といった悩みが現場から多く聞かれます。
一般的に、人事部門が存在しない、あるいは人事制度が十分に整備されておらず、賃上げ(昇給)が経営者の主観に偏りがちな中小企業では、社員の不満や不安を招くケースが少なくありません。少人数で運営されるクリニックも、こうした構造的な課題を抱えやすい環境にあるという指摘があります。
クリニックの「スタッフの賃上げ」を成功に導く3つの秘訣
ここでは、スタッフの定着率向上につながる、賃上げ成功の秘訣を解説します。これから賃上げを検討している開業医も、すでに実施した開業医も、ぜひチェックしてみてください。
1.評価に紐づいた賃上げの基準を導入する
本来、賃上げや昇給を決定する際には、人事評価制度に基づき、役割に応じてスタッフの能力や成果を公正に評価し、その結果を賃金に反映させることが理想です。
スタッフは評価制度があることによって、勤務先のクリニックが何を基準として働きぶりを評価するのか、何を大切にしているかが理解しやすくなります。その結果、スタッフの給与に対する納得感が増し、仕事へのモチベーションにつながるでしょう。
また、評価基準は賃上げのためだけでなく、理念やビジョンを実現するための手段という捉え方もできます。
評価基準を設定する際には、院長が掲げる価値観や方向性といった経営理念やビジョンを一度整理して言語化し、それを評価項目に落とし込み連動させることが大切です。理念と評価制度に一貫性があることでスタッフは目標を理解しやすくなり、自律的な行動や成長意欲の向上に寄与します。
2.賃上げの根拠となる評価基準をスタッフ全員に周知する
賃上げを最大限活用するために評価制度が有用なことは、前述したとおりです。しかし、手間をかけて評価制度を導入したにもかかわらず、それがスタッフの間に周知されていなければ、意味がありません。
入職時だけでなく、日常業務の中でも評価制度の存在を積極的にスタッフに伝え、浸透させることが重要です。そうすることで、「リーダーになれたから昇給できた」「あの人は技術を上げたから給与が増えた」など、賃上げした際の透明性、公平性、納得性が大きく変わります。
また医療求職者の中には、給与だけでなく「自分が成長できるか」「適正に評価されるか」といったことにこだわって働く人も少なくありません。
求人広告や採用面接でも、人事評価制度に基づいて頑張りを認める風土があることをアピールすることで、採用のミスマッチや離職を防ぐだけでなく、採用ブランディングの強い一手になるはずです。
3.賃上げはフィードバックまでが完了形と心得る
「賃上げ」=「コスト増」ではなく、人材への投資です。しかしその意図・理由をきちんと伝えていなければ、賃上げしたとしても、スタッフは納得感が持てないだけでなく、職場への不信感につながる可能性があります。
そこで有用なのが、フィードバック面談です。賃上げを実施する際は、院長などの評価者がスタッフと対話を行い、業務の振り返りとあわせて評価結果を共有する時間を設けましょう。スタッフにとって賃上げへの透明性がぐんと高まるだけでなく、業務改善や成長の促進、信頼関係の構築にもつながります。
一般企業では、時間は30分~1時間ほどが理想とされていますが、忙しい医療機関ではその時間を捻出するのは難しいかもしれません。そんな場合は短くても良いので実践してみてください。
賃上げするクリニックが知っておきたいトレンドキーワード
一般の大企業・中小企業ともに賃上げの流れが加速し、社会全体で「構造的な賃上げ」が定着しつつある昨今。クリニックもまた、賃上げとは無関係でいられません。
そこで、賃上げをする上でクリニックが知っておきたい、注目のキーワードをピックアップしました。
令和6年(2024年)度診療報酬改定
「令和6年(2024年)度診療報酬改定」とは、物価高騰や人材不足などを背景に、医療従事者の賃上げや医療DX化を後押しする内容が盛り込まれた改定のこと。
医療・介護・障害福祉の3分野の報酬が同時に見直される、6年に一度の「トリプル改定」の年でもあり、大きな注目を集めました。
今回の改定の目玉施策の一つとして新設されたのが、「ベースアップ評価料」です。これは、看護師や薬剤師など対象スタッフの賃金を改善している医療機関に対し、診療報酬に加算される仕組みで、人材流出の防止に一定の効果が期待されています。
一方で、「改定だけでは十分な賃上げにはつながりにくい」「人件費の増加が経営に影響を及ぼしている」といった後ろ向きの声も聞かれます。
実際に、クリニック未来ラボ編集部が実施した「診療報酬改定に関する開業医調査」(※)でも、「改定によって収益が減少した」と回答した開業医のうち、約5割もがその要因の一つとして「医療従事者の賃上げ」を挙げています。
このことからも、賃上げと経営の両立に向けて、戦略的な判断が求められます。
※出典:クリニック未来ラボ「診療報酬改定に関する開業医調査」。調査対象/全国の30~90代の医科の開業医433人、調査期間/2025年3月17日~3月26日、調査方法/インターネットでのパネル調査
令和6年度税制改正による賃上げ促進税制
「賃上げ促進税制」とは、企業やクリニックが従業員の給与を一定以上引き上げた場合に、法人税や所得税の一部を控除できる制度のことです。
その目的は、令和6年度診療報酬改定と同様に、医療機関の賃上げです。「ベースアップ評価料」で収入面を強化し、「賃上げ促進税制」で税制面を優遇するというように、国は制度的に連動する形で医療従事者の処遇改善をバックアップしています。
国は医療機関に対し、2024年度に2.5%、2025年度に2.0%のベースアップを方針として掲げており、社会全体で賃上げの必要性が高まっているといえます。
人事評価制度
「人事評価制度」とは、スタッフの働きぶりを適切に評価する仕組みのことです。
具体的には、評価軸に基づき、業務遂行能力や勤務態度、成果などを公平に評価し、賃上げ(昇給)や昇格、人材育成に反映するというものです。
単なる査定の仕組みではなく、離職防止や定着率の向上、成長の促進、職場の信頼関係の構築など、さまざまなメリットが期待できるため、近年は医療業界でも関心が高まっています。
評価軸の設計に不安がある場合は、「ドクターズ・ファイル クリニコ」のようなクリニック専用の人事評価システムを活用するのも選択肢の一つです。評価項目のテンプレートなどが用意されているため、スムーズな導入を後押ししてくれます。
クリニックへの「人事評価」の導入で
スタッフの生産性向上を実現!
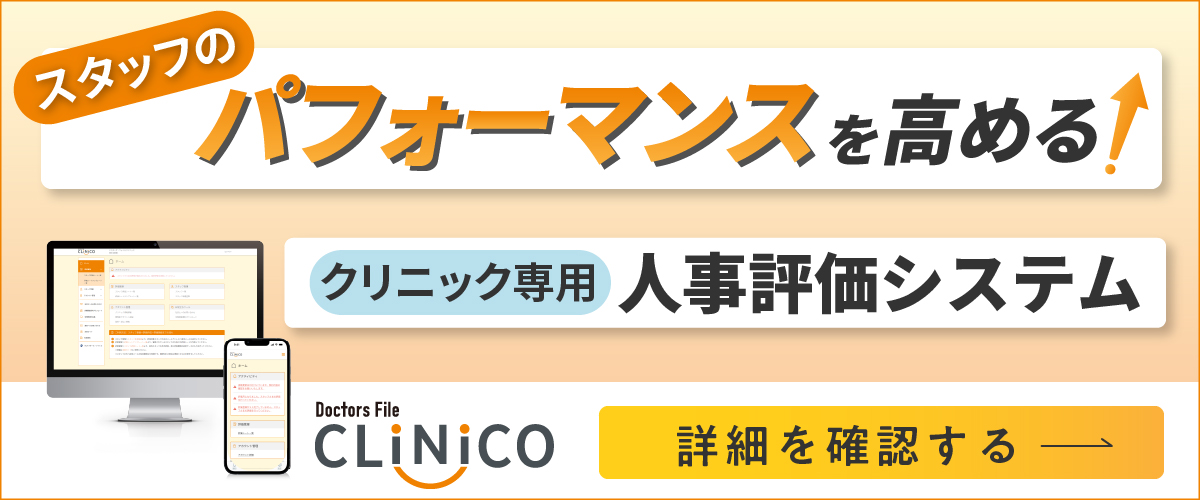
まとめ
年々、クリニックの競争が激化する中、質の高い医療サービスを提供し、地域医療に貢献し続ける上で、欠かせないのがスタッフの力です。
定着率向上のためには、賃上げの際に公平な評価やフォローアップを忘れず、一人ひとりと向き合ってみてください。
また、今回取り上げたスタッフの賃上げなど人材や組織に関する課題を抱えている場合は、一人で悩まず、専門家を頼ることもお勧めです。
クリニック向け総合サービスプラットフォーム「ドクターズ・ファイル」が提供する「人事の外来」サービスでは、人事(HR)の専門家から、人材採用や育成、評価、組織開発、スタッフとの信頼関係の構築などへのアドバイスが受けられます。
人事に関するお悩みやご相談がある方は、ぜひ一度、「人事の外来」へお問い合わせください。
<文・取材構成>
内藤 綾子(ないとう・あやこ)
ライター。生命保険企業に3年間勤務した後、編集プロダクションにてライターとしての活動を開始。雑誌、書籍、Webで、健康・医療分野およびHR・企業広告・妊娠・出産・育児・教育・生活分野などの企画・記事制作業務に携わる。