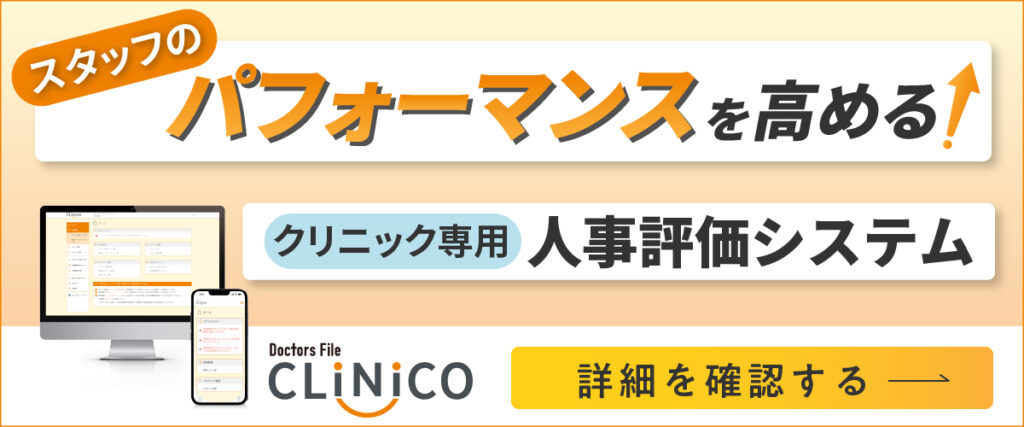医療接遇で言葉遣いが大切な理由
ほとんどの患者やその付添人は、治療や検査への不安を抱えて来院することから、医師・看護師など医療従事者の接遇に敏感です。そのため、質の高い医療サービスを提供したにもかかわらず、接遇が至らなかったためにクリニックの評価が下がってしまうこともあるようです。そこで初めに、医療接遇で言葉遣いが大切な理由を説明します。
言葉遣いの重要性を理解し、患者やその家族への接遇に生かしましょう。
患者の気持ちに寄り添い不安を取り除く
医療接遇における言葉遣いが大切な理由は、患者の気持ちに寄り添い不安を緩和する必要があるためです。医療機関を受診する患者の多くは、痛みを感じていたり、どのような治療や検査を受けるのか不安を抱えていたりと、通常より神経質な状態にあります。
心身ともにつらい状況にあるため、医療従事者による丁寧で正しい言葉遣いは患者の不安や緊張を和らげ、クリニックの信頼性を高める効果が期待できます。
また、言葉は丁寧であっても、真摯さに欠けているとかえって患者の不安を増してしまう場合があります。大切なのは、患者の気持ちに寄り添ったコミュニケーションです。その姿勢が伝われば、安心感を与えられ、患者が悩みや症状について話しやすい雰囲気をつくることができるでしょう。
患者との信頼関係の構築
接遇において適切な言葉遣いを徹底することで、医療のプロフェッショナルとして患者との信頼関係を深められます。ただし、医師だけの対応が良くても、受付や看護師などの対応が適切でなければ長期的な信頼関係を築きにくくなります。信頼を獲得するためには、クリニックで働く全員が適切な言葉を用いて患者と接することが大切です。
また、医療のように専門性の高い業種では、医師や看護師といったサービス提供者よりも利用者のほうが低い立場にあると考える患者も少なくありません。そのため、医療従事者が威圧的な言葉遣いをすると患者は委縮し、症状や悩みについての詳細な情報共有や質問をためらう原因となり、結果として診断の精度が下がるリスクがあります。
接遇における言葉遣いは、丁寧な言葉を使うだけではなく、医療従事者が対等な目線で、患者の訴えにしっかり向き合う姿勢を示すことがポイントです。
クリニックのスタッフが徹底すべき言葉遣いのポイント
続いて、医療従事者の言葉遣いの具体的なポイントを説明します。医療現場での言葉遣いは、販売業やサービス業のような一般的な接遇とは異なり、患者の不安や苦痛に寄り添い信頼関係を構築する目的があります。
また、患者一人ひとりに合わせて、使い分けをしないと患者の本音を引き出すことができません。どのような場面で言葉の使い分けが必要なのかといったポイントを理解して、スタッフの接遇に役立ててみてください。
敬語(尊敬語・謙譲語・丁寧語)
まず販売業やサービス業などの業種と同様、医療接遇においても敬語を用いた丁寧な言葉遣いをすることが肝要です。正しい敬語を使うことで、相手に礼儀正しい印象を与えられます。ご存じのように、敬語には大きく3つの種類があります。次の表をもとに、敬語の使い分けができているかを確認しましょう。
| 敬語の種類 | 特徴 | クリニックでの会話例 |
|---|---|---|
| 尊敬語 | 主語は相手。自分よりも相手を立てて、敬う言い方 お(ご)~なる、~れる・られる、いらっしゃる、おっしゃる など | 患者や家族の動作を表現 「○○様でいらっしゃいますね」 「当院をご利用になるのは初めてですか?」 |
| 謙譲語 | 主語は自分。自分を謙遜して相手を立てて、敬う言い方 ~させていただく、お ・ご~する、~いたす、伺う、拝見する、参る、申す など | 医療従事者の動作を表現 「保険証を確認させていただきます」 「間もなく医師が参ります」 |
| 丁寧語 | 主語は問わない。相手や内容を問わず、丁寧に言って敬う言い方。幅広いシーンで用いられる ~です、~ます、~ございます、お(ご)〇〇 など | 患者や家族、医療従事者の動作を表現 「こちらが検査室です」 「領収書でございます」 「お問い合わせいただき、ありがとうございました」 |
また、医療接遇として不適切な敬語や、誤った敬語の使用にも注意が必要です。
| 不適切・誤った敬語 | 正しい敬語 |
|---|---|
| すみません | 申し訳ございません |
| 了解しました | 承知いたしました、かしこまりました |
| 会計窓口から呼びます | 会計窓口からお呼びいたします |
ただし詳しくは後述しますが、患者によっては、医療従事者が正しい敬語を徹底しすぎることで、冷たい印象を受ける人もいます。敬語を用いながらも、よそよそしくならないよう相手の年齢や性格に合わせて声のトーンや表情などを工夫し、温かなコミュニケーションを心がけると良いでしょう。
クッション言葉
クッション言葉は枕詞ともいわれ、本題に入る前に添える、患者への配慮や思いやりを示す短い言葉です。患者とのコミュニケーションをスムーズにしたり、不安な気持ちを和らげたりできる表現でもあります。次の表で、患者に質問したり、依頼したりする際に使えるクッション言葉をまとめました。
| 使うシーン | クッション言葉の例 |
|---|---|
| 患者に質問するとき | ・差し支えなければ ・ご迷惑でなければ ・失礼ですが ・お伺いしたいことがあるのですが ・もしよろしければ |
| 患者に依頼するとき | ・お手数をおかけしますが ・お忙しい中恐れ入りますが ・ご都合がよろしければ ・ご足労おかけしますが ・ご面倒でなければ |
このようにクッション言葉を使うとより手寧さが加わり、気遣いや思いやりを示すことができるでしょう。ただし、クッション言葉を多用しすぎると冗長になり、かえって不快感を与えてしまう可能性もありますので、状況に応じて柔軟な使い分けが必要です。
患者への説明では専門用語を避ける
医療現場では、患者に対して専門的な医療用語を避けてわかりやすい言葉を使用することも重要です。
患者やその家族に説明する際、医療従事者はかみ砕いて話しているつもりでも無意識に専門用語を使っているケースがあります。そのような場合、患者側は意味が理解できず、質問しづらくなったり、相談しづらくなったりしてしまいます。例えば「嚥下」は「食べ物などの飲み込み」、「予後」は「病気の見通し」などのように、医療用語は簡単な言葉に言い換えるように心がけましょう。
このとき、患者の反応を見ながらゆっくりと話し、説明の途中でわからないところはないかを適宜、確認することも大切です。もし言葉だけでは伝わりづらそうな場合は、イラストや写真、模型などを用いて視覚的に説明するのも一手です。「わかりやすく説明してくれるから安心できる」と印象づけられ、信頼の構築にもつながります。
医療接遇で言葉遣いに気をつけるメリット
次に、医療従事者が言葉遣いに気をつけるメリットを解説します。言葉遣いに注意するメリットを理解して、無理なく自然体で接遇ができるよう役立ててください。
院内のコミュニケーションがスムーズになる
医療接遇におけるスタッフの言葉遣いの改善には、クリニック内でのコミュニケーションがスムーズになるというメリットがあります。年齢や立場に関係なく、敬語をベースとした丁寧なコミュニケーションを取ることにより摩擦が減り、職場の雰囲気が改善され、互いを思いやれる良好な関係構築につながります。また、スムーズな連携により、コミュニケーション不足による医療ミスの防止にも役立ちます。
また、多くの患者が出入りする院内では、スタッフ同士の会話漏れを完全に防ぐことは困難です。万一、スタッフ同士のくだけた会話や、配慮に欠けた物言いを聞かれてしまった場合、患者からの印象を大きく損ねる危険があります。スタッフが診療時間中は常に丁寧な言葉を使うようルールを設けることで、こういったリスクを回避し、患者からの印象を良くする効果も期待できるでしょう。
新規患者の増加とリピート率の向上
常にきちんとした言葉遣いを徹底し、患者に寄り添う温かい雰囲気を保っているクリニックは、患者に好印象を与えられます。
質の高い医療技術の提供も重要ですが、配慮ある言葉遣いによって適切なコミュニケーションが取れていると、患者は「丁寧に診てくれる」「寄り添って話を聞いてくれる」と感じ、大きな安心感を得られます。その結果、提供する医療サービスへの良い評価につながり、地図検索サービスのGoogleマップやSNSなどでの口コミ評価の向上も期待できるでしょう。引いては新規患者の増加やリピート率が向上し、患者に愛されるクリニックとして長く地域医療に貢献できるはずです。
医療接遇で言葉遣いに気をつけるデメリットとその対策
一方で、クリニックが接遇における言葉遣いをルールとして定めることによるデメリットも存在します。最後に、そのデメリットと対策についてご紹介しましょう。
スタッフの心理的負担が増える
接遇における言葉遣いをクリニック内でルール化した場合、常に丁寧な敬語とクッション言葉を用い、間違ってはならないというプレッシャーがスタッフの心理的負担につながる場合があります。また、言葉を選ぶあまり自然なコミュニケーションが取れなくなるケースや、会話時間の延長による業務効率の低下を招く可能性もあります。
医療接遇における言葉遣いの改善に取り組む際は、まずはスタッフにその目的をしっかり理解してもらうとともに、無理のない範囲で取り入れ、強制的にならないよう注意してください。
機械的な対応になる
細かくマニュアルを作成して言葉遣いをルール化した場合、画一的な対応によってスタッフの個性や人間味が薄れてしまう危険があります。特に敬語にあまり慣れていない若手スタッフにマニュアルを順守させようとすると、つい機械的な対応になったり、二重敬語や過剰敬語になったりしてしまう場合も少なくありません。
接遇における言葉遣いを改善する本来の目的は、患者の気持ちに寄り添い、不安を軽減することです。マニュアルを作成する場合は細かすぎず、一定の裁量をスタッフに委ねるようにしましょう。またスタッフには、患者に対して思いやりや配慮を示すことが最も重要であることを明確に伝えることも大切です。
患者に堅苦しい印象を与える
丁寧な言葉遣いを徹底しすぎると、患者に堅苦しい印象を与えてしまう場合があります。どれほど提供する医療サービスの質が高くても、過剰な敬語によって「事務的で人間味がない」「他人行儀で冷たい」、さらには「へりくだりすぎて馬鹿にしているのか」などとマイナスの印象を与えてしまった場合、患者に安心を与えるどころか、信頼関係を築くことは困難になるでしょう。
ルールに縛られ過ぎず、患者一人ひとりを見て、どの程度丁寧な言葉遣いにするのか、どのような接し方が適切なのか、スタッフ一人ひとりが頭で考えて行動できるようにすることが重要です。
まとめ
今回は、医療接遇において言葉遣いが大切な理由について解説しました。
医療接遇の5原則の一つである言葉遣いは、患者の不安軽減や信頼関係構築のために重要です。一方で、医療従事者同士も丁寧な言葉遣いを意識することで、コミュニケーションの質が高まり、結果的に患者満足度の向上や新規患者の増加が期待できます。
定期的な研修やミーティングを行い、クリニック全体で医療接遇についての理解を深め、患者に寄り添った言葉遣いを意識してみてください。(クリニック未来ラボ編集部)