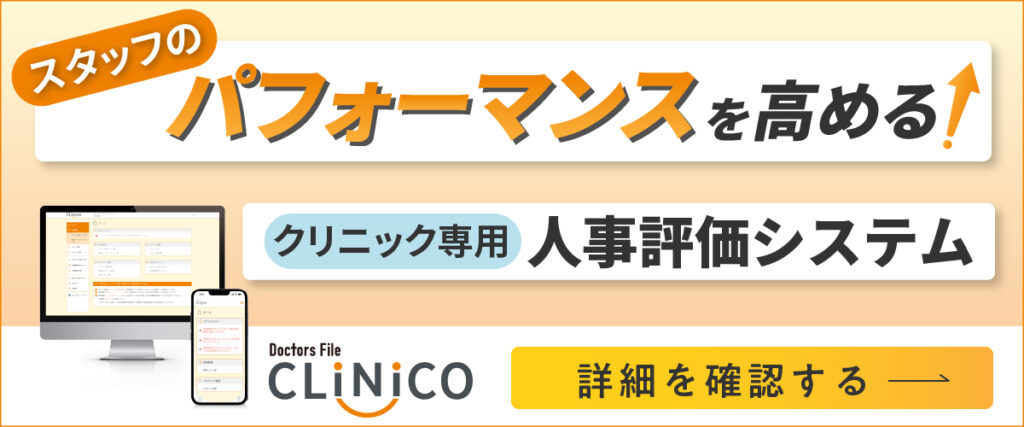医療接遇マナーの基本5原則
まずはチェックリストをより深く理解するために、医療接遇において重要な5つの要素について知っておきましょう。
- 表情
- あいさつ
- 言葉遣い
- 身だしなみ
- 態度
この5つは「接遇マナーの基本5原則」といわれます。これらの要素を総合的に網羅した接遇を行うことで、医療現場において患者の不安を軽減し、信頼関係を築くことにつながります。例えば、どれだけ医療従事者が礼儀正しくあいさつをしても、無表情や愛想のない態度では、患者が良い印象を抱くことは難しいでしょう。ほかにも、身だしなみの乱れはルーズな印象を与えるだけでなく、保健衛生上の観点からも好ましくありません。
医療接遇の目的は、一人ひとり違う患者やその家族の気持ちに寄り添い、過ごしやすく、安心して通院できる環境を作り出すことです。基本5原則を医療従事者が徹底することで、病状や年齢に応じて言葉の選択や声のトーン、話すスピードを柔軟に調整できたり、患者の状態を迅速に見極めることができたりするようになります。
そして接遇に取り組む上で大事なのが、人によって接遇マナーの質にばらつきが出ないよう、医師を含めたスタッフ全員で同じ指標のもとに実践することです。次に紹介するチェックリストを活用し、クリニック全体で接遇スキルの向上に取り組んでみてください。
医療接遇チェックリスト
医療接遇をクリニック全体で意識するには、スタッフの接遇力を可視化し、対策することが重要です。院長である医師が求める接遇レベルや医療接遇の目的を明確にし、スタッフ全員のスキルアップをめざすと良いでしょう。
なお、クリニックによって大切にしている価値観や理念、患者層は異なるため、紹介するチェックリストを参考に、自院に適切な項目や数を設けることをお勧めします。
「表情」に関する接遇チェックリスト
表情は患者に安心感を与える大事な要素です。日々、スタッフ自身がどのような表情をしているかを、客観視することが大切です。
□ 患者と接する際は、常に穏やかな表情を心がけているか
□ マスクの着用時も、目元で笑顔を表現できているか
□ 患者の表情や様子に合わせて、適切な表情で対応しているか
□ 疲れていても無表情や険しい表情を見せないように注意しているか
□ 患者と目を合わせる際は、威圧的にならない柔らかな視線を意識しているか
「あいさつ」に関する接遇チェックリスト
あいさつはコミュニケーションの第一歩です。相手の目を見て、適切なタイミングで温かみのある声かけを心がけましょう。特にマスク着用時は表情が伝わりにくく、患者が不安を感じやすいため、より一層の配慮が必要です。
□ 患者を見かけたら、先にあいさつをしているか
□ 積極的に患者の名前を呼んでいるか
□ 「おはようございます」「こんにちは」など、時間帯に応じた適切な挨拶をしているか
□ 声の大きさは適切で、相手に聞こえやすい音量を保っているか
□ 患者の年齢や状態に合わせた挨拶の仕方ができているか
□ 退室時に「失礼いたします」「ありがとうございました」などのあいさつをしているか
「言葉遣い」に関する接遇チェックリスト
丁寧な敬語を中心としたコミュニケーションは、患者の不安を和らげ、話しやすい空気作りに役立ちます。患者との会話では目を合わせ、しっかりと理解していることを態度で示すことが大事です。書類の受け渡しの際は、用途の説明や利用の案内など、丁寧な対応を意識してください。
□ 敬語を適切に使用しているか
□ 医療用語を避け、わかりやすい言葉で説明しているか
□ クッション言葉を適切に活用しているか
□ 高齢者には、ゆっくりと明確な発音で話しているか
□ 子どもには、年齢に応じたわかりやすい言葉を選んでいるか
□ 否定的な表現を避け、前向きな言葉に言い換えるよう心がけているか
「身だしなみ」に関する接遇チェックリスト
身だしなみは、患者からの第一印象を大きく左右します。清潔感を心がけ、信頼感の醸成に努めましょう。また整った身だしなみは、医療従事者自身の気分も上げ、働く意欲の向上にもつながります。
□ 制服や白衣にシミや汚れ、シワ、ほころびがないか
□ 髪型は清潔で、髪色は自然な色を保っているか
□ アクセサリーは控えめで、必要最小限にしているか
□ 爪は短く切り、マニキュアはしていないか
□ 健康的なナチュラルメイクになっているか
□ 香水やアロマなど、強い香りを控えているか
□ 服を着崩していないか
□ 長い髪はまとめ、清潔感のあるヘアスタイルになっているか
「態度」に関する接遇チェックリスト
傾聴や共感など、患者に接する際の態度も重要です。医療従事者が高圧的にならず、患者がリラックスして話しやすい雰囲気を作りましょう。
□ 患者に対して常に誠実な対応を心がけているか
□ 患者の話を最後まで傾聴しているか
□ 頷きや相づちで共感する姿勢を見せているか
□ 急いでいても慌ただしい態度を見せていないか
□ 書類の受け渡しは丁寧に、両手で行っているか
□ 私語を慎み、職場にふさわしい態度を保っているか
□ 腕や脚を組むなど高圧的なポーズを取っていないか
□ 貧乏ゆすりをしていないか
□ 患者の話を遮って自分の話をしないよう心がけているか
接遇チェックリストの効果的な活用方法
続いて、患者満足度を上げるために、接遇チェックリストを使ってスタッフ全員の接遇レベルを向上させる具体的な方法についてご紹介します。
日常的な活用方法
朝礼や定例ミーティングの際に5分程度の時間を設け、チェックリストの項目を全員で確認しましょう。特に重要な項目や、最近気になる点について重点的に共有することで、クリニック全体における意識統一を図ることができます。
評価制度の導入
月に1回程度、接遇についての評価を行う時間を30分程度設けましょう。この時間では、まず前半で各スタッフに自己評価を行ってもらい、後半で相互評価を行います。
自己評価としては、チェックリストを用いて過去1ヵ月の自身の接遇を振り返り、できている点と改善が必要な点を明確にします。自己評価結果は個人で記録として残し、時系列での成長を実感できるようにすることが効果的です。
また相互評価のパートでは、2〜3人のグループを作り、互いの接遇を観察・評価し合う機会を設けます。第三者の視点からの評価により、自分では気づかない改善点を発見できます。この際、スタッフ同士で批判し合うのではなく、前向きで建設的なフィードバックを共有するよう徹底することが重要です。
評価に基づく具体的な改善計画
月に1回程度の評価をした後は、得られた結果をもとに向こう1ヵ月の具体的な改善計画を立案しましょう。例えば、短期・中期・長期の3パターンで目標を立てる方法が効果的です。
- 短期目標(1週間):クリニックとして特に重要で即座に改善できる項目を3つ選択し、実践を促す
- 中期目標(1ヵ月):クリニックとして克服すべき苦手項目を改善するための具体的な行動を計画
- 長期目標(3ヵ月):さらなる改善の余地がある項目を中心に、理想的な接遇の実現に向けたスタッフ全体のスキルアップを計画
定期的な効果測定と見直し
接遇力の向上は一朝一夕には実現できるものではありません。患者から今よりも信頼される医療機関となるためには、チェックリストを活用した地道な取り組みを継続することが大切です。そこで、定期的に以下の指標を確認し、チェックリストの活用効果の測定をお勧めします。
- 患者満足度調査の結果
- クレーム件数の推移
- リピート率の変化
- Google マップなどのレビューの推移
- スタッフの接遇に対する意識変化(アンケート)
また、チェックリストは一度作ったらそのまま使い続けるのではなく、実状に合わせて、柔軟に内容を更新することで、チェックリストの形骸化を防止できます。効果測定によって得られた情報をベースに、以下の観点から定期的なチェックリストの見直しを行うことが肝要です。
- 患者からのフィードバック
- 医療環境の変化
- スタッフからの提案
- 接遇トレンドの変化
スタッフ全員が接遇の重要性を理解し、主体的に改善に取り組む姿勢を持つことが、成功への鍵です。定期的な振り返りと改善を繰り返すことで、理想的な医療接遇の実現をめざしましょう。
新人教育への活用
チェックリストは新人教育に有効活用できます。新入職員の教育では、このチェックリストを基準として具体的な指導を行います。項目ごとに実践的なトレーニングを実施し、段階的なスキルアップを図ります。
| 導入研修(入職1週間) | チェックリストの各項目の意図と目的を詳しく説明し、まずは医療接遇の基本と重要性を理解してもらう |
| 実践トレーニング(1ヵ月目) | 「身だしなみ」「あいさつ」など各カテゴリーの重要項目を実際の業務の中で実践できているか確認 |
| スキルの定着(2~3ヵ月目) | 定期的な振り返りと改善点の指南を行い、これまでのトレーニングで培った接遇スキルをより洗練させる |
新人教育では、チェックリストを単なる評価ツールではなく、スキルアップのための指針として活用することが重要です。教育担当者は、成長段階に合わせた指導の実施や、良い点を積極的に評価してモチベーションの維持を重視することで高い効果が見込めます。
一般的な接遇と医療接遇の違い
最後に、一般的な接遇と医療接遇の違いについても解説します。
一般的な接遇は、飲食店やホテルなどのサービス業において必要なスキルであるのに対し、医療接遇は医療現場に特化したスキルで、患者の抱える不安を解消させるための細かな応対を指します。
患者の不安に寄り添う
一般的な接遇は、サービスを受けたくて楽しみに訪れる客を対象に、おもてなしの心で満足度を高めることが目的です。しかしその一方で、医療接遇は不安を抱える患者に寄り添い、安心感を提供することが目的というように、両者には違いがあります。
クリニックを訪れる患者の多くはいつも以上に緊張し、不安や心配を抱えているものです。「何の病気なのか」「治療は痛いだろうか」「医師との相性は大丈夫だろうか」「どんな診療方針なのか」「病気は進行していないか」など、その中身は一人ひとり異なります。
そのため、医療接遇では職場全体で患者一人ひとりの気持ちを理解し、寄り添う姿勢を持つことが重要となります。
患者と対等な関係を築く
本来、患者と医療従事者は対等な関係であるべきですが、医療現場では、医療従事者が医療を提供し、患者が医療を受けるという立場上、どうしても両者の間に上下関係が生まれやすい傾向にあります。
このような状況が恒常化した場合、患者は不安や痛みを訴えづらく、信頼関係の構築が困難になるため、診療が円滑に進みにくくなります。それが引いてはクリニックの評価を下げる要因となり、長期的な視点で見たときに、クリニックの成長にも影響を及ぼしかねません。
医療接遇によって些細なことでも質問しやすい良好な関係性を築くことができれば、「このクリニックは信用できる」「安心して通いやすい」という評価につながり、さらには「今日も来て良かった」という患者満足度の向上に結びつきます。
必要以上の接遇は逆効果になる
医療接遇の目的はサービス業のような顧客の満足度向上ではなく、患者の抱える不安を緩和することにあります。そのため、やりすぎには注意が必要です。過度な接遇は医療従事者の負担やストレスを増やし、現場の疲弊を招くだけでなく、一方の患者にとっても「ここまで丁寧にしなくてもいいのに」「面倒な患者だと思われているのだろうか」のように負担となる可能性があります。
医療接遇に取り組む際に大切なのは、医療従事者が日常業務の中で適切なケアの時間を確保する工夫です。患者の心情を理解した上で、必要とされる範囲の対応を心がけることが、医療接遇の本来の目的といえます。
まとめ
医療接遇の改善は、クリニックの評価向上と患者満足度の向上につながる重要な要素です。本記事で取り上げた医療接遇マナーの基本5原則である、表情、あいさつ、言葉遣い、身だしなみ、態度を意識し、チェックリストを活用することで、効果的に接遇を改善できるはずです。
チェックリストの活用では、定期的な自己評価と相互評価を実施し、具体的な改善計画を立てることが重要です。また、新人教育のツールとしても効果的に併用できます。
クリニック全体で接遇の重要性を理解し、継続的な改善に取り組むことで、地域住民から愛される医療機関をめざしましょう。(クリニック未来ラボ編集部)
<執筆者プロフィール>
クリニック未来ラボ編集部
クリニック未来ラボは、開業医、開業を目指す勤務医・医学生に向けたクリニック経営支援メディアです。独自の視線で調査・研究し、より良い医院経営に役立つ情報として発信。「開業医白書」をはじめ、診療報酬改定や医師の働き方改革、医療従事者の転職動向など、医院経営に関する調査レポートも公開しています。